
こんにちは、みちのくです☀️
今回も引き続き、災害の記事が多いです。

慶雲に改元されてからずっとこんな感じですね…

あとは、国守の任官記事も目立ちます。
三河守など、史上初めて任官された記録もあり、大宝律令施行後5年経って初めて国守が中央から派遣されたと見られます。
慶雲3年(丙午・西暦706年)現代語訳・解説
任官(式部卿)
秋 7月11日(壬子) 従四位上巨勢朝臣太益須を式部卿に任じた。
以從四位上巨勢朝臣太益須爲式部卿。
巨勢太益須は『日本書紀』に以下の記述があります。
・朱鳥元年(686)10月2日 大津皇子に大舎人として仕えていたが、皇子の謀反事件に縁座した容疑で捕えられる。このとき、ほか30人余りが逮捕されるが、その後に詔により赦された。
・持統天皇3年(689)2月26日に、判事(裁判官)に任じられる。
・同年6月2日に、撰善言司(ためになる先人の善い言葉を集めて書にするための編纂事業を担った官司)に任じられる。

撰善言司は、幼少の文武天皇に帝王教育を行うための書を作ろうとしたのではないかとされています。残念ながら完成はしなかったようですが

えらい人の言葉を集めた本を作ろうとしたんですね。
任官(美濃守)
7月20日(辛酉) 従五位下笠朝臣麻呂を美濃守に任じた。
以從五位下笠朝臣麻呂爲美濃守。
| 国名 | 国力 | 種別 | 守の官位相当 | 主な相当位置 |
| 美濃国 | 大国 | 東山道 | 従五位上 | 岐阜県南半部 |
笠麻呂は、大宝4年(704)正月7日に正六位上から従五位下に昇叙されています。
山火事
7月24日(乙丑) 丹波国(京都府中部、兵庫県東部など)・但馬国(兵庫県北部)2国の山に火災があった。そのため使いを遣わして幣帛(神への供え物)を神祇(天地の神々)に奉った。すると雷声がたちまち発し、火を叩くこともなく自然と鎮火した。
大倭国宇智郡狭嶺山(奈良県五條市大深町)に火災があった。叩いてこれを消火した。丹波。但馬。二國山火。遣使奉幣帛于神祇。即雷聲忽應。不撲自滅。
大倭國宇智郡狹嶺山火。撲滅之。
7月下旬は今の暦で9月上旬頃なので、空気が乾燥しやすい季節であり、雨が長期間降っていなかったとすると土壌や草木が異常乾燥し、自然発火で山火事が発生する可能性があるようです。
ただ、引っかかるのは宇智で火災が発生したことです。宇智というと、2月23日に天皇が行幸したばかりであるため、人為的な放火の可能性があると思います。不徳の天皇として、度重なる災異を招いたことへの抗議で何者かが宇智を狙って放火したのかもしれません。

のちの聖武天皇の時代にも明らかに放火だろうという火災の事例があります。このときも国内が疲弊しきっており国民の不満が溜まっていた状況でした。
もちろん、他の場所でも山火事が発生していて火がつきやすい条件が揃っていたのもあり、宇智で発生したのは偶然かもしれませんが…。

同じ日に丹波国と但馬国にも火災がありますから、ちょっとわからないですね…。
狭嶺山は、江戸時代の享保21年(1736)に成立した『大和志(大和の地誌)』によると嶺大深村の山であるとし、同村は現在の奈良県五條市大深町にあります。

すごく山奥ですね。この村を抜けても延々と紀伊山地が続いて大きな集落はなく、道のりは険しそうです。当時人は住んでいたのでしょうか…?
任官(大倭守)
7月27日(戊辰) 従五位下阿倍朝臣真君を大倭守に任じた。
以從五位下阿倍朝臣眞君爲大倭守。
| 国名 | 国力 | 種別 | 守の官位相当 | 主な相当位置 |
| 大倭国(大和国) | 大国 | 畿内 | 従五位上 | 奈良県 |
阿倍真君は、慶雲2年(705)12月27日に従六位下から従五位下に一気に4階昇叙されたという記録があります。大宝3年(703)6月5日から大倭守を務めていた大伴男人に代わり任命されました。

官位相当は従五位上ですが、1階低い従五位下で任命されてます。
祥瑞(白鹿)の献上、飢饉の発生
7月28日(己巳) 周防守従七位下引田朝臣秋庭たちが白鹿を献上した。
諸国に飢饉が発生した。六道【西海道を除く】に使いを遣わしてすべて賑恤(被災者を救うため金品を支給すること)させた。周防國守從七位下引田朝臣秋庭等獻白鹿。
諸國飢。遣使於六道。〈除西海道。〉並賑恤之。
周防守は、周防国(山口県東南部)の国司の長官です。官位相当は従五位下ですが、従七位下という低い位階の官人が任命されているのが気になります。本来、従七位下では周防国(上国)は四等官の3番目の「掾」にしかなれませんが、律令制施行当初はこのような例もあったようです。従五位以上の官人の人数が不足していのかもしれません。
白鹿は祥瑞(吉兆として現れる動植物や自然現象)です。

神様が、天皇の治世が善であるとして祥瑞が出現する一方、さらなる飢饉も発生し…朝廷は混乱していたでしょうね

神様の気持ちはどうなっているのでしょう…
九州地方に大風の被害
大宰府が次のように言上した。「管内の9国3嶋に日照りと大風がありました。樹が引き抜かれ、秋の作物が損なわれました」と。よって、使いを遣わして巡省させ、その被害の最も甚大な者の調役(調と肉体労働)を免除した。
大宰府言。所部九國三嶋亢旱大風。拔樹損稼。遣使巡省。因免被災尤甚者調役。
収まらない山火事
8月3日(甲戌) 越前国(福井県)が次のように言上した。「山火事が収まりません」と。よって、使いを遣わして部内の神に奉幣(神に物品をお供えすること)しこれを救わせた。
越前國言。山災不止。遣使奉幣部内神救之。

国内に蔓延する厄災も極限状態まで来ている感がありますね、、、、

災害の記事があまりにも多すぎて、しんどくなってきました。
任官(遣新羅大使)
8月21日(壬辰) 従五位下美努連浄麻呂を遣新羅大使に任じた。
以從五位下美努連淨麻呂。爲遣新羅大使。
美努浄麻呂は慶雲2年(705)12月27日に正六位下から従五位下に一気に4階昇叙されたという記録があります。
伊勢斎宮の交代
8月29日(庚子) 三品田形内親王を遣わして伊勢大神宮に侍らせた。
遣三品田形内親王。侍于伊勢大神宮。
「伊勢大神宮に侍らせた」とは伊勢の斎宮に選んだという意味でしょう。斎宮とは、天皇に代わって天照大神をお祭りする女性で、未婚の内親王(時に女王)の中から占い(亀の甲羅を火で炙ったときにできる亀裂の形状によって占う)によって選定されました。

この占いを「亀卜」といい、占いによって物事を決することを「卜定」といいます。
『日本書紀』によると、田形内親王は天武天皇の皇女で、母親は蘇我氏で名前を大蕤娘(おおぬのいらつめ)といいます。同母の兄に穂積親王、姉に紀皇女がいます。

穂積親王はこのとき「知太政官事」として太政官の統括者を務めています。
(慶雲2年(705)9月5日)

最有力皇族の妹さんなんですね。文武天皇からは叔母にあたるわけですか
伊勢斎宮はこれまで天智天皇皇女の泉内親王が遣わされていましたが、今回で田形内親王に交代されたようです。斎宮は天皇の崩御や近親者が亡くなると辞職することとなりますが、今回はなぜ交代することとなったのか、理由は不明です。
任官(三河守)
9月3日(甲辰) 従五位下坂合部宿禰三田麻呂を三河守に任じた。
以從五位下坂合部宿祢三田麻呂爲三河守。
| 国名 | 国力 | 種別 | 守の官位相当 | 主な相当位置 |
| 三河国 | 上国 | 東海道 | 従五位下 | 静岡県西半部 |
坂合部三田麻呂は慶雲2年(705)12月27日に正六位上から従五位下に昇叙された記録があります。
田租の法
9月15日(丙辰) 七道に使いを遣わして初めて田租の法を定めた。1町ごとに15束を徴収することとした。役丁(労役に従事する成年男性)を点検した。
遣使七道。始定田租法。町十五束。及點役丁。
田租についての規定は大宝律令に既にあるため、今回「初めて」定めたというのは違和感がありますが、これは『続日本紀』を編集している段階(奈良時代後期から平安時代初期)において実施されている現制度が、この時初めて定められたという意味かと思います。
実際、本来の律令には1町ごとに徴収する稲は22束となっており、数量が異なっています。災害による不作を考慮して徴収する量を減らしたのでしょう。
次回の記事
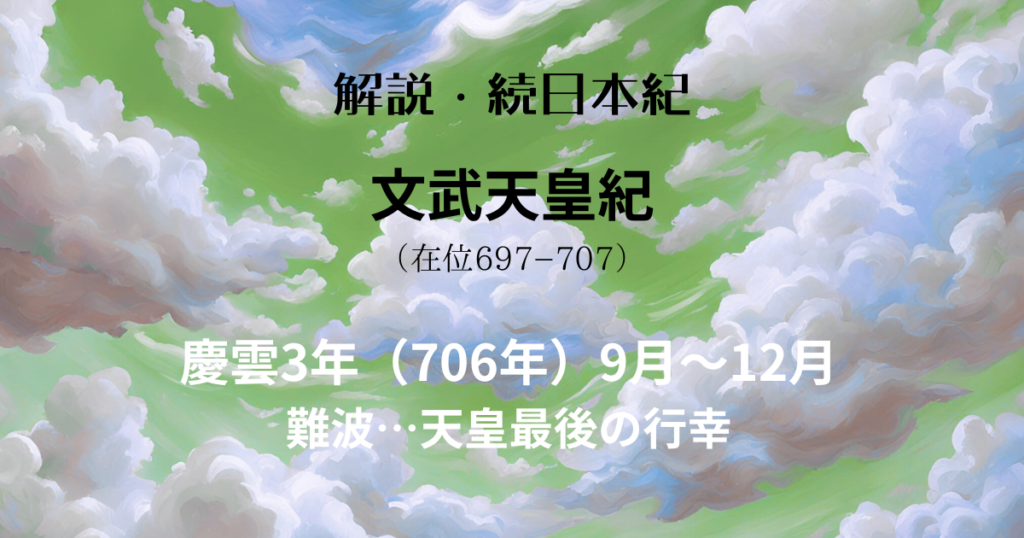

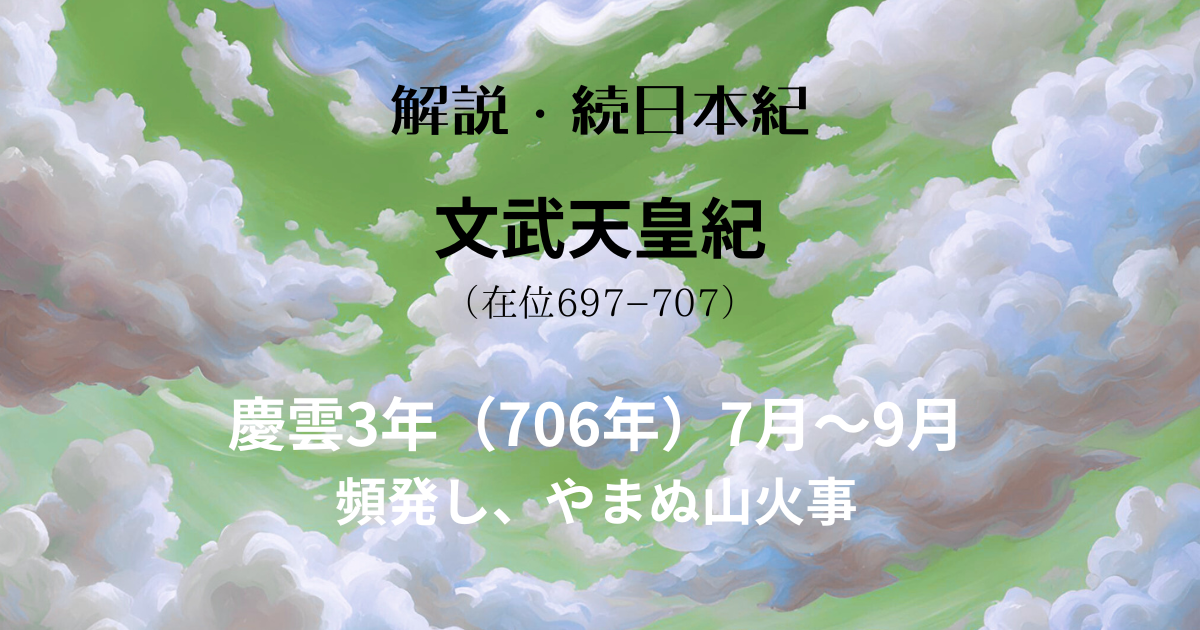


コメント