
こんにちは、みちのくです☀️
今回は『続日本紀』文武天皇の即位記事についてとりあげます。

よろしくお願いします♨️
文武天皇元年(丁酉・西暦697年)現代語訳・解説

受禅・即位
8月1日(甲子) 文武天皇は、受禅し、即位した。
受禪即位。

「禅」には「ゆずる」という意味があります。

ゆずりを受けるから、「受禅」なんですね!
初めて聞いた言葉ですけど、漢字の意味を調べると意外とカンタン✨
文武天皇(皇太子珂瑠皇子)は、今の天皇である持統天皇から譲りを受けて、新たに天皇として即位しました。天皇がその地位を次の継承者に譲ることを譲位といい、譲位した前天皇を太上天皇(略して上皇)といいます。
また、この8月1日(甲子)を即位の日としたことにも意味があります。甲子(きのえね、こうし)の日は、60日でひとめぐりする干支(かんし、えと)の最初の日であり、物事の始まりを象徴する日です。しかもその甲子の日が月初の8月1日にあたっているので、超吉日というわけです。

15歳のフレッシュな天皇が即位するのにぴったりな日ですね!

まさに、持統天皇と文武天皇は「満を持して」この日に臨んだことでしょう。
文武天皇の漢詩
ここで、文武天皇が詠まれた漢詩を1首紹介します。「述懐」という、自らの心中を詠った漢詩です。15歳で即位した文武天皇は、当時どのような心境だったのか?天皇の心中を知ることができるとても貴重な史料です。

『懐風藻』という日本最初の漢詩集からご紹介
『懐風藻』文武天皇 御製漢詩
○原文
「述懐」
年雖足戴冕 智不敢垂裳 朕常夙夜念 何以拙心匡
猶不師往古 何救元首望 然毋三絶務 且欲望短章○書き下し
「懐を述ぶ」
年は戴冕に足ると雖も 智は敢て裳を垂れず。
朕常に夙夜念うに、何を以てか拙心を匡さんと。
猶往古を師とせずは、何ぞ元首の望みを救わんと。
然も三絶の務め毋く、且く短章に望まんと欲す。○大意
「心中の思いを述べる」
年は冠を戴くのに十分であるが、その知識は必ずしも天下が治まる程度ではない。
朕は常に朝から晩まで思うに、何をもってつたない心をただせば良いのだろうかと。
やはり、古くからの教えを師としなければ、国の元首としての望みをかなえることはできないだろう。
しかも三絶(すり切れるまで書物を読むこと)の努めもないのだから、しばらくは短い文章からでも読んでいきたいと思う。

天皇として即位して、どうすれば国を治めていくことができるのか?…やはり自分に必要なのは勉強だ!と感じておられたみたいです。
その中で「とりあえずは短い文章から始めよう!」という現実的な目標を決めるところに文武天皇のお人柄が感じられて距離感がグッと縮まります♨️

とても真面目なお方だったのだなと思いますね。
ご自身の置かれた立場を自覚しようとふんばっているようなイメージです。
『懐風藻』には他に文武天皇の漢詩「月を詠む」、「雪を詠む」の2首が収載されています。
即位の詔(宣命文)
8月17日(庚辰) 文武天皇は、次のように詔した。
(宣命体)
「『これは現御神として、大八島国所知天皇の大命であるぞ』と宣し賜う大命を、ここに集まり侍している皇子たち、王たち、臣下たち、百官の者たち、天下の公民は皆々承知せよ。
『『高天原から降臨された後、遠い昔から代々に天下を治められてきた天皇(の地位)は、天つ神の御子として、天に坐す神のご委任に従いお治めになってきた”天津日嗣高御座の業“であるぞ』と、仰せられた大八島国所知倭根子天皇(先代の持統天皇)が私に授けられた貴く、高く、広く、厚い大命を受け賜り、かしこまり、この食国天下を調え賜い平らげ賜いて、天下の公民を恵み賜い、撫で賜わんと神ながらにして思っているぞ』と、宣賜う大命を皆々承知せよ」詔曰。現御神〈止〉大八嶋國所知天皇大命〈良麻止〉詔大命〈乎。〉集侍皇子等王等百官人等。天下公民諸聞食〈止〉詔。高天原〈尓〉事始而遠天皇祖御世御世中今至〈麻弖尓。〉天皇御子之阿礼坐〈牟〉弥繼繼〈尓〉大八嶋國將知次〈止。〉天〈都〉神〈乃〉御子隨〈母〉天坐神之依〈之〉奉〈之〉隨。聞看來此天津日嗣高御座之業〈止。〉現御神〈止〉大八嶋國所知倭根子天皇命授賜〈比〉負賜〈布〉貴〈支〉高〈支〉廣〈支〉厚〈支〉大命〈乎〉受賜〈利〉恐坐〈弖。〉此〈乃〉食國天下〈乎〉調賜〈比〉平賜〈比。〉天下〈乃〉公民〈乎〉惠賜〈比〉撫賜〈牟止奈母〉隨神所思行〈佐久止〉詔天皇大命〈乎〉諸聞食〈止〉詔。

よく分からないですけど、威厳とか厳かな雰囲気はすごく伝わります!💦

即位した文武天皇は国の頂点に立つ者として、天下の全ての人々に詔を宣布しました。
宣命とは、天皇のお言葉を和文の形式で、口頭により伝えたものです。宣命の読みが特殊な理由はそういうことで、口により発した日本語を紙に文字起こししたためなのです。これは当時使われていた日本語がどう発音されていたかを知ることのできる、大変重要な史料です。
ちなみに、この文武天皇即位の宣命が現存最古の宣命文となっています。この詔の中で15才の文武天皇は、先代であり、祖母でもある持統天皇からの教えをかしこまって守り、この国を統治し、人民を恵み慈しんでいく決意を天下の人々に対し宣言しました。

「公民」と書いて「おおみたから」とは…?

天皇にとって国民とは「大いなる宝」なんですね。
皇帝とか、帝王と聞くと独裁者をイメージする人も多いかもしれませんが、日本の天皇はその点が違いますね。

大切にされてるんですね。なんだか心強いというか…安心します。
「公民」と書いて「おおみたから」と訓ませているのは非常に大きな歴史的意義があります。「天下の公民を恵み賜い、撫で賜わん」とあるように、天皇にとって国民は「大いなる宝」なのです。この事実は、当時から1300年後の現代においても全く変わるところがありません。
(続き)
「『ここを以て、百官の者たち、四方の食国を治め奉れと任命した国々の宰たちに至るまでの者たちは、天皇が朝廷の敷き賜われた国法に反することなく、明るく、清浄で、正直で、誠の心を持ち、進んでたるみ怠ることなく務め仕え奉ること』と、宣り賜う大命を皆々承知せよと詔る」是以百官人等四方食國〈乎〉治奉〈止〉任賜〈幣留〉國々宰等〈尓〉至〈麻弖尓。〉天皇朝庭敷賜行賜〈幣留〉國法〈乎〉過犯事無〈久。〉明〈支〉淨〈支〉直〈支〉誠之心以而御稱稱而緩怠事無〈久。〉務結而仕奉〈止〉詔大命〈乎〉諸聞食〈止〉詔。
続いて文武天皇は、すべての官人と、朝廷から国の東西南北に派遣され政治を行う「みこともち」たちに訓示を行いました。「みこともち」とは「御言持ち」。すなわち天皇のお言葉(御言)を代行する任務を負っているということです。のちに「国司」と呼ばれる人たちにあたります。

みこともち…なんかかっこいい!

(無言でうなずく)
(続き)
「『故に、このような状を承知し悟って勤勉に仕え奉る者は、その働きぶりの随に、誉めて品々(官位)を上げることとする』と、宣り賜う天皇の大命を皆々承知せよと詔る」
よって、今年の田租、雑徭ならびに庸の半分を免除する。また、今年から3年の間、大税の利息を徴収しない。老人に恤(恵み)を施す。また、親王以下百官の者たちに差をつけて物を下賜する。諸国に毎年放生(家畜や捕えた生き物を放すこと)を行わせる。故〈乎〉如此之状〈乎〉聞食悟而款將仕奉人者其仕奉〈礼良牟〉状隨。品品讃賜上賜治將賜物〈曾止〉詔天皇大命〈乎〉諸聞食〈止〉詔。仍免今年田租雜徭并庸之半。又始自今年三箇年。不收大税之利。高年老人加恤焉。又親王已下百下百官人等賜物有差。令諸國毎年放生。
単語解説
雑徭 ぞうよう。国司の権限で人民(男性のみ)を徴発し、1年に60日間を基本としてインフラ整備などの肉体労働を課した。
庸 よう。麻布の納入を課した。本来は京に出向き、10日間の労役に従事するというものだった。
大税 おおちから。各国の倉庫(正倉)に備蓄される稲。正税ともいう。この倉庫の稲を人民に貸し付け、その利息が徴収された(出挙)。
参考書籍など
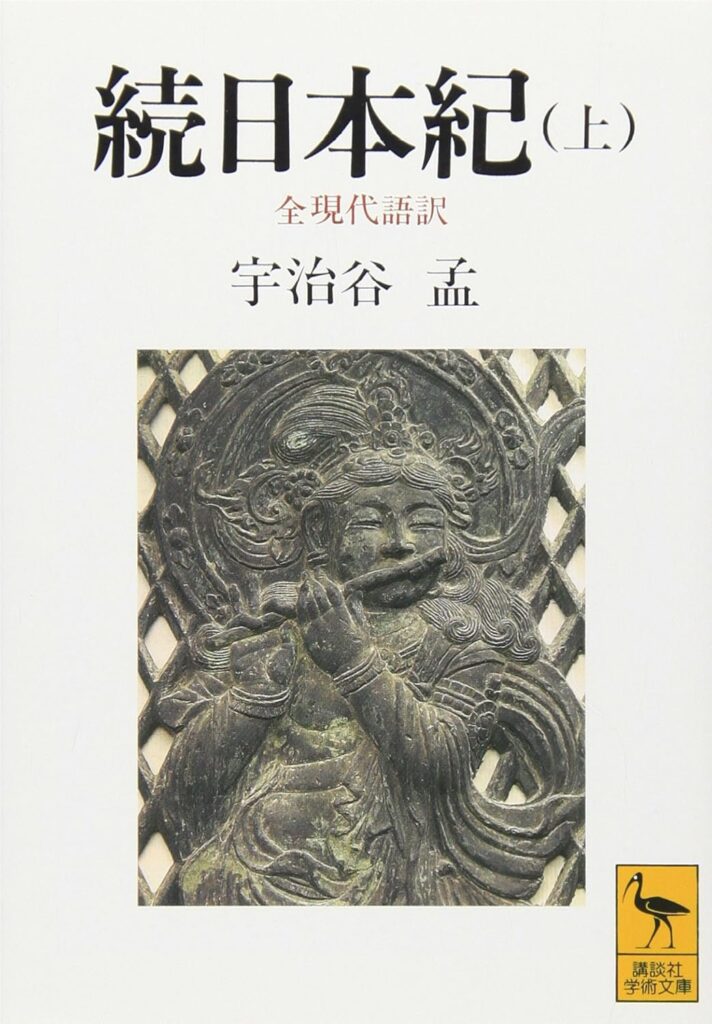
次回は

文武天皇元年(697年)8月20日、文武天皇の妃についての記事をとりあげます☀️
↓のバナーから飛べますのでぜひご覧くださいね!

次回もよろしくお願いします♨️
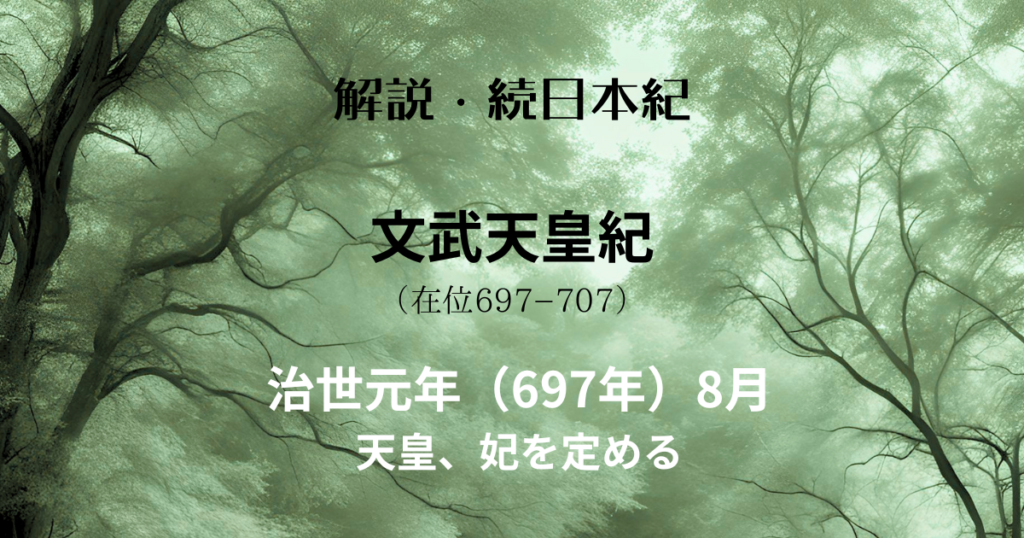

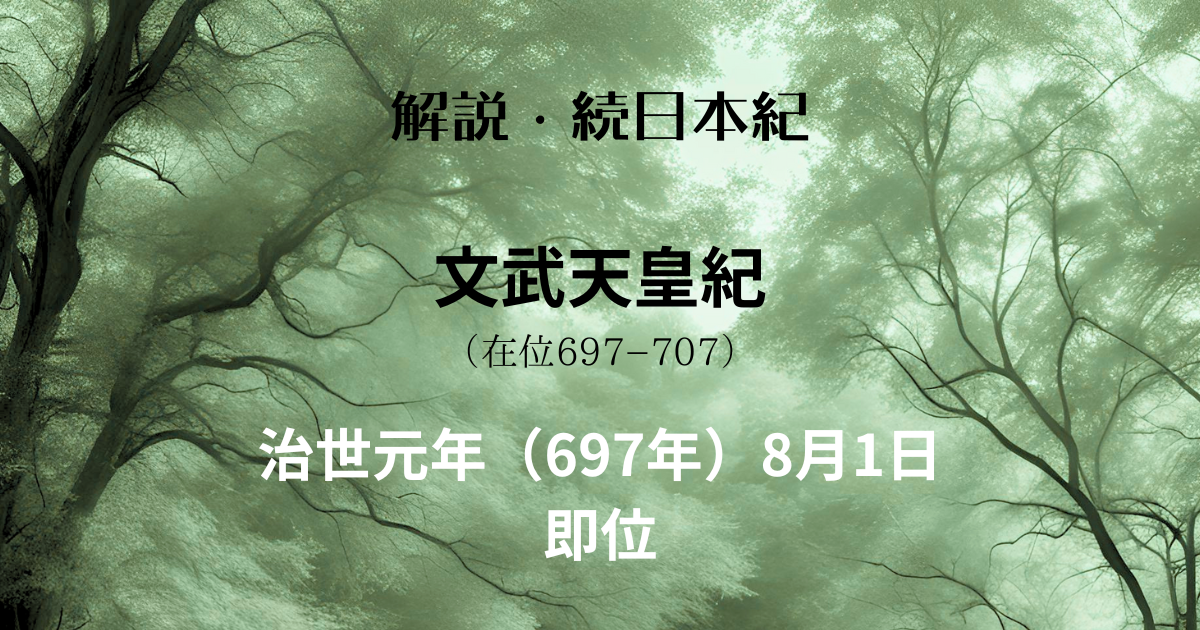


コメント