
こんにちは、いづみです♨️
蝦夷征討軍が編成されましたけど、前回の更新では音沙汰がなかったですね?

今回は実際に征討が行われたとみられる記事があり、詳細不明ながら、結果として征討軍は一定の戦果をあげたようです。それでは見ていきましょう☀️
和銅2年(己酉・西暦709年)現代語訳・解説
任官(陸奥守)、兵器の移送

秋 7月1日(乙卯) 従五位上上毛野朝臣安麻呂を陸奥守に任じた。
蝦狄を征伐するため、諸国に命じて兵器を出羽柵に運び送らせた。
以從五位上上毛野朝臣安麻呂爲陸奥守。
令諸國運送兵器於出羽柵。爲征蝦狄也。
これまで陸奥守は前年(708)3月13日(乙未)に上毛野小足が任じられていました。同じ氏族からの任命ということで上毛野氏は東北経営についてのノウハウや人脈が豊富だったのかもしれません。

上毛野氏は東国の上野国(群馬県)を本拠とする氏族です。
蝦夷征討直前のタイミングで任命されるのは意味ありげですね。
この年の3月5日(壬戌)に遠江、駿河、甲斐、信濃、上野、越前、越中などの国に対し蝦夷征討の兵が徴発され、将軍が任命されました。
「蝦狄」という単語ですが、「狄」という字が使われている場合は、日本海側のエミシのことを指し、「蝦夷」の場合は太平洋側のエミシを指しており『続日本紀』はこの両者を使い分けています(区別していないこともあるようですが)。
出羽柵、「柵」というとガードレールやバリケードのようなものをイメージしますが、おそらく当時の柵とはもっと大規模な城と呼べるような軍事施設であったはずです。また、柵付近に「柵戸」として人民を移住させた事例(『日本書紀』大化3年(647)是年条など)もあり、人が生活できる行政機能をも備えた、いわば「城下町」のようなものであった可能性があります。

そんな出羽柵ですが、当時存在していた場所は特定されていません。
天平5年(733)に出羽柵は今の秋田城跡の場所に遷されます。つまり、秋田城の前身が出羽柵ということです。

のちに秋田城になるということは、やはりもともとの出羽柵も「城」としての軍事機能だけでなく、人が居住する空間や行政機能を備えていたと見る事ができますね。
軍船を蝦夷征討の軍営に送る
7月13日(丁卯) 越前(福井県)、越中(富山県)、越後(新潟県)、佐渡(新潟県佐渡市)の4国に船100艘を征狄所に送らせた。
令越前。越中。越後。佐渡四國船一百艘送于征狄所。
征狄所は文字通り蝦狄征伐の拠点となる場所ですが、具体的な場所は分かりません。ただ、船を送らせたということは、日本海沿岸に設けられたことは間違いないでしょう。

わざわざ「征狄所」と呼んでいるところから、出羽柵とはまた別の場所に設けられたのだと思いますが、利便性を考えれば出羽柵と距離はそう離れてはいないのではないでしょうか。

ということは出羽柵も海の近くに作られた可能性が高いですね。
和同開珎銀銭の廃止

8月2日(乙酉) 銀銭を廃して銅銭のみを流通させることとした。
廢銀錢。一行銅錢。
発行されたばかりの和同開珎の銀銭ですが、流通停止となりました。銀銭の流通開始が前年の8月ごろと仮定すると、わずか1年で流通が終わったことになります。そういうことなので、和同開珎銀銭は銅銭と比べて極端に出土した点数が少ないです。

銅銭はこれまで6000枚以上発見されていますが、銀銭の方は全国を合わせても50枚程度しか見つかっていないそうです。

なぜこんなに短期間で終わってしまったのでしょうか?

理由は書かれていないため推測になりますが、銀が非常に貴重で価値が高く銭貨として使用するには過ぎたものと政府や市中に認識されたからではないでしょうか。

以前、銀銭の価値は銅銭の4倍というレートが決められました(和銅2年3月27日)が実際にはそれ以上だったということなのでしょうか…?

まず、当時の日本では銀はごく限られた場所でしか採掘できず、ほとんどを唐や新羅からの輸入に頼っていたものと思われます。そのため、流通に必要な量を確保できず銀の実際の価値が高すぎて「銅銭の4倍」という政府の建前がそもそも維持できなかったのだと思います。
なお、以後平安時代までの日本で発行された12種類の銭貨(いわゆる「皇朝十二銭」)は全て銅銭であり、銀銭が作られることは一度もありませんでした。

和同開珎銀銭は貨幣経済初期の時代ならではの試行と実験があったと感じさせられます。
河内鋳銭司の官人の待遇について
(続き)
太政官は次のように処分した。「河内の鋳銭司に所属する官人の賜禄(給与)と考選(官人の昇進考査)は、すべて寮に准ずることとする」と。
太政官處分。河内鑄錢司官属。賜祿考選。一准寮焉。
官司には序列があり、上から官・省・職・寮・司となっています。鋳銭司は「司」でありながら「寮」に所属する官人の待遇を受けられるようになったということです。和同開珎の利用を推進するため、鋳銭司が重要視されていたことの表れでしょう。
凱旋する将軍
8月25日(戊申) 征蝦夷将軍正五位下佐伯宿禰石湯、副将軍従五位下紀朝臣諸人は、事(蝦夷征討)が終わって朝廷に帰還した。天皇は2人を召して特にこれを褒め、優寵(特別の愛顧を受けること)し給われた。
征蝦夷將軍正五位下佐伯宿祢石湯。副將軍從五位下紀朝臣諸人。事畢入朝。召見特加優寵。
この年の3月5日に徴兵と将軍の任命が行われ、越後と陸奥の蝦夷征討軍が編成されました。戦線の過程はまったく不明ですが、任務は無事に遂行されたようです。ところで、征蝦夷将軍の佐伯石湯と副将軍の紀諸人は越後方面の蝦夷征討に派遣されたわけですが、この記事には陸奥方面の将軍「陸奥鎮東将軍」に任じられている巨勢麻呂の名前が見えません。

陸奥方面では思ったような戦果を上げられなかったとか、戦闘がそもそも起きなかったとか、そもそも準備が整わず出発できなかったとか…?

詳細は一切不明です。ただ、将軍の巨勢麻呂は今後も元明天皇のもと順調に出世していくので、能力がなかったというわけでもなさそうです。

今回の戦いは日本海側が主戦場になった可能性が高いというのもありますもんね。陸奥方面ではあまり戦闘自体が起きなかったのかも。
平城宮に行幸

8月28日(辛亥) 車駕(又は「しゃが」。天皇の乗る車。転じて天皇自身を指す)は平城宮に行幸した。駕に従った京畿の兵衛の戸(世帯)の雑徭(地方における60日間の肉体労働)を免除した。
車駕幸平城宮。免從駕京畿兵衛戸雜徭。
元明天皇は、造営が進められている平城宮に行幸しました。目的はもちろん視察です。前年(708)9月14日(壬申)から9月20日(戊申)にも平城宮とその一帯の地形の視察を行っています。

遷都が行われるのは710年ですから、あと1年…。
その日が間近に迫ってきてますね!
兵衛は律令によると、通常時はシフト制により京内の門番を行い、行幸があればこれに従って列をつくり警護を担当。定員は全体で800人と定められています。
大倭守などに叙位、百姓を巡撫する
9月2日(乙卯) 大倭守(のちの大和守)従五位下佐伯宿禰男に従五位上を授けた。造宮大丞従六位下台忌寸宿奈麻呂に従五位下を授けた。
この日、車駕は新京の百姓を巡撫(各地を巡って人民を鎮め安んずること)し給われた。
授大倭守從五位下佐伯宿祢男從五位上。造宮大丞從六位下臺忌寸宿奈麻呂從五位下。
是日。車駕巡撫新京百姓焉。
造宮大丞は造宮省の第3のポストとみれ、台宿奈麻呂(うてな の すくなまろ)という人物は従六位下から従五位下に4階一挙に昇叙したことからかなりの功績があったとみられます。台氏は大陸からの渡来氏族で、その名は国の四方を望み見るための台をつくることを生業としたのが由来のようです。このことから、平城宮の宮殿づくりにも一定の知識と技能を有する氏族だったのかもしれません。

「新京の百姓」とあるように、すでにこの時点で京域には街路や住居があり人が住み始めていたことがわかります。
造宮省官人に物を賜う
9月4日(丁巳) 造宮将領以上の者にそれぞれ差をつけて者を賜った。
賜造宮將領已上物有差。
造宮将領が具体的にどのような職掌であったのかは分かりませんが、「将」も「領」も「率いる」という意味がありますから、造宮に従事する労働者の現場監督のようなものでしょうか。

造宮省の官人に物を賜り、平城京のある大倭国の国守の位階を上げ、そして新京の百姓を巡撫。このことから、造営は順調に進んでいるみたいですね♨️
平城宮から藤原宮に還幸
9月5日(戊午) 車駕は平城から還幸した。
車駕至自平城。
造営中の平城宮の視察を終え、元明天皇は飛鳥の藤原宮に帰還しました。
将軍たちに禄を賜う
9月12日(乙丑) 征狄将軍たちに、それぞれ差をつけて禄を賜った。
賜征狄將軍等祿各有差。
エミシの征伐を完了した将軍たちに特別の褒賞が贈られました。今回の征討で任命された将軍は先述の通り、陸奥鎮東将軍と征越後蝦夷将軍とその副将軍の3人ですが、ここでも「征狄」とあるため太平洋側蝦夷の征討司令官である陸奥鎮東将軍は含まれていません。

もはや陸奥鎮東将軍は征討に出発したのかすら怪しくなってきましたね…
従軍者の税を免除
9月26日(己卯) 遠江、駿河、甲斐、常陸、信濃、上野、陸奥、越前、越中、越後などの国士(徴発された兵士をいう)のうち、征伐に50日以上従事した者に1年間の税を免除した。
遠江。駿河。甲斐。常陸。信濃。上野。陸奥。越前。越中。越後等國軍士。經征役五十日已上者。賜復一年。
東海・東山道に巡察使を派遣
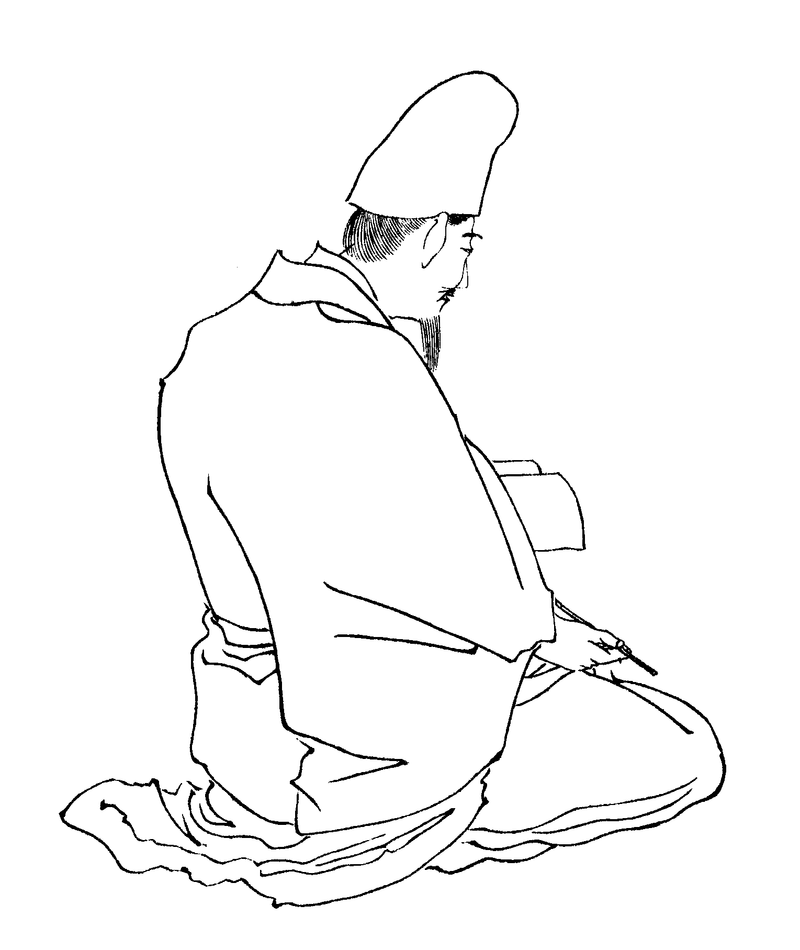
(続き)
従五位下藤原朝臣房前を東海、東山の2道に遣わして関剗(関所と剗。『令義解』によると、剗は人の往来を規制するための堀と、先を尖らせた木を並べて配置した侵入防止柵)を検察し、その国の風俗を巡省(巡回して様子や状況を視察すること)させた。よって、伊勢守正五位下大宅朝臣金弓、尾張守従四位下佐伯宿禰太麻呂、近江守従四位下多治比真人水守、美濃守従五位上笠朝臣麻呂にそれぞれの国の田10町と穀200斛、衣1襲を賜った。その業績を褒めてのことである。
遣從五位下藤原朝臣房前于東海東山二道。検察關剗。巡省風俗。仍賜伊勢守正五位下大宅朝臣金弓。尾張守從四位下佐伯宿祢大麻呂。近江守從四位下多治比眞人水守。美濃守從五位上笠朝臣麻呂。當國田各一十町。穀二百斛。衣一襲。美其政績也。
久しぶりの巡察使の派遣。前回の派遣は慶雲2年(705)4月5日(甲寅)のため、およそ4年半ぶりとなります。巡察使とは律令に定められた臨時の官で、以下のように規定されています。
律令 巻第2 職員令
2(太政官条)
巡察使 職掌は、諸国を巡り察ること。常置はしない。内外の官のうち清正灼然(人となりが清廉で、明快であるさま)たる者を仮に任じること。巡察の事情やその人数は臨時に勘案して決めること。
藤原房前は以前(大宝3年(703)正月2日(甲子))にも東海道巡察使に任じられたことがあり、その経験を買われたとみられます。
伊勢国(三重県)、近江国(滋賀県)、美濃国(岐阜県南半部)には関所があり、反乱などの有事に通行を遮断して中央を防衛する役割を持っていました。尾張国には著名な関所は見えませんが、東国への玄関口となっており交通の要衝といえる土地条件です。そのため関所に準ずる施設があった可能性が高く、その施設を「剗」と称したのではないかと思います。

関所は主に山間部につくられますが、平地が多く山間部が少ない尾張国には関所ではなく「剗」という通行規制の堀と柵を作って往来を監視・制限していたのではないでしょうか。

漢字辞典には「剗」は削るという意味があるようです。
堀を掘ったり先端を尖らせた木製の柵をつくるのも「削る」行為と関連がありますね。
和銅2年に入ってからというもの、全国の要地へ朝廷が関与し、位階を上げたり官人に物を下賜するといった記事が多いです。例えば、大宰府に対するもの(2月1日、5月5日、6月20日)、東北蝦夷対策(3月5日)、新羅使との懇談(5月27日)そして今回の巡察使派遣。

思うに遷都が近いため、これに乗じた反乱や不穏な動きを制するために全国的に手回しをし、混乱を未然に防ぐ意図があったのではないかと思います。

あえて関所のある国に巡察使を送っていますから、間違いないですね!
次回の記事
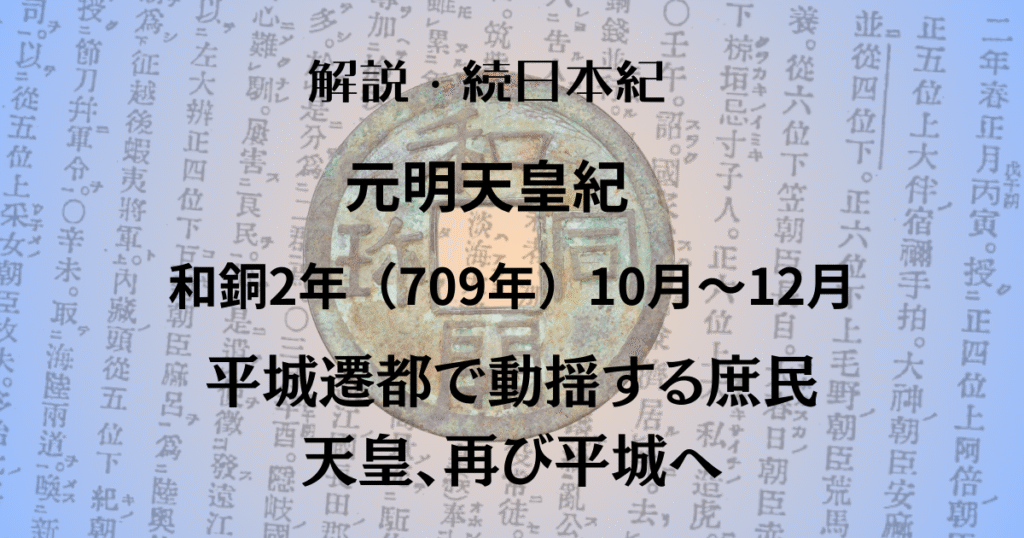

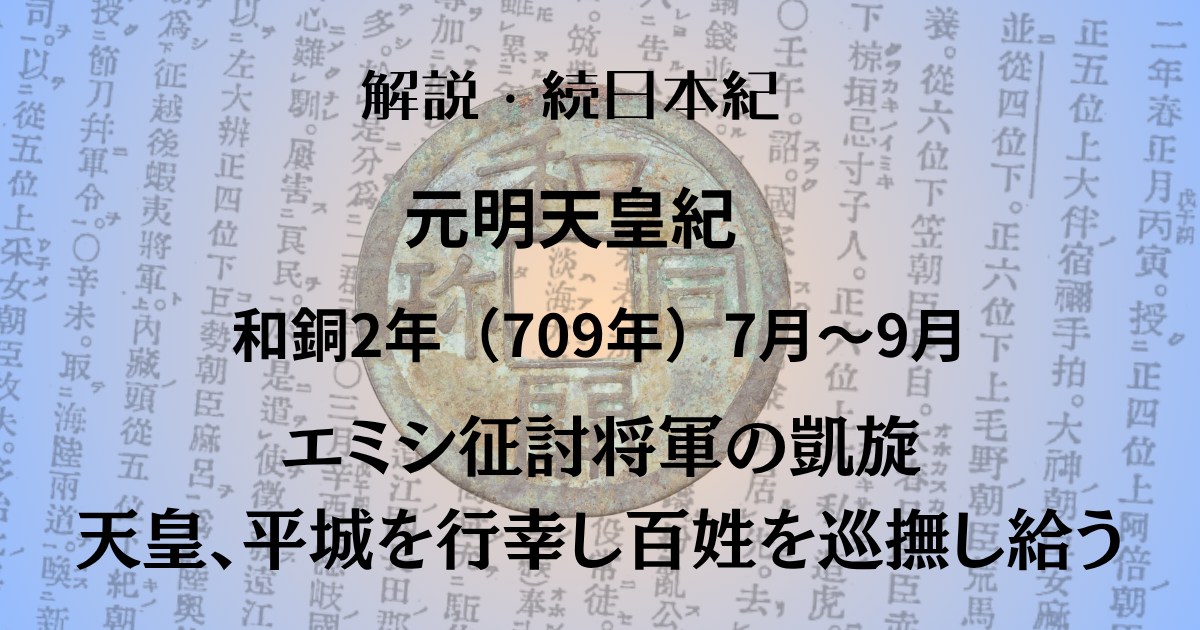
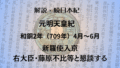
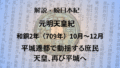
コメント