
こんにちは、いづみです♨️
今回で慶雲3年は最後になります。

難波への行幸記事から始まりますが、これに動員された騎兵の数やこのときに詠まれた和歌など当時の具体的な行幸の様子をうかがうことができます。
慶雲3年(丙午・西暦706年)現代語訳・解説
難波に行幸
9月25日(丙寅) 天皇は難波に行幸した。
行幸難波。
難波は現在でも大阪の地名としてよく知られており、「なんば」と読まれることも多いですが、当時の読みは「なにわ」のみでした。
初めて史書に難波の名が見えるのは『日本書紀』神武天皇紀の東征紀、戊午年2月11日(丁未)条です。神武天皇の軍が九州から発し、瀬戸内海を通って難波碕に到ったとき、この碕の潮の流れが非常に早いことをもって「浪速国」と名付けました。『書紀』は「今、『なにわ』と呼ぶのはこの『なみはや』が訛ったものである」としています。

今でも大阪市浪速区として残っていますね!

難波宮跡。現在の陸地は埋立や河川の改修工事のため、文武天皇の時代とはかなり異なっています。当時は難波宮のすぐ東側に河内湖という海につながる入江があり、今とまったく違う景色があったようです。
この地は神武天皇がそうであったように、瀬戸内海を通じて海路で大和と山陽道・南海道(四国)や大宰府、さらに朝鮮半島や大陸をつなぐ航路になっており、我が国にとって重要な交通の要衝でした。そのため、第15代応神天皇や第36代孝徳天皇の時代には難波に宮が置かれたこともありました。
律令制施行後は摂津国の領域となり、この地を擁する摂津は特別行政区のような扱いを受け、その重要性は変わりませんでした。文武天皇が難波を訪れるのは治世3年(699)正月22日以来7年ぶりです。

そして、これが文武天皇の最後の行幸となりました。

な…それはつまり、そういうことですか…。
そういえば、文武天皇の治世は697年〜706年となってますね。終わりが近づいているんですね
このときの行幸を歌った和歌が『万葉集』に収められています。
慶雲3年丙午に難波の宮に幸す時 志貴皇子の作らす歌(歌番号:64)
葦辺行く鴨の羽交ひに霜降りて寒き夕は大和し思ほゆ
(大意)
葦のある池のほとりを行く鴨の、両羽の交わるところに霜が降るような寒い夕べには、都のある大和のことが遠く偲ばれる

旧暦9月25日は今の11月の上旬ごろにあたるため、夕方にはかなり冷え込んだことでしょう。

寒さを表現するのに鴨の羽の交わるところに降りる霜を持ち出すとは、目の付け所が斬新ですね!志貴皇子にしか詠めない歌でしょう
志貴皇子は天智天皇の子です。皇子の子はのちに第49代光仁天皇として即位することとなりますが、今はまだまだ遠い未来の話です。
藤原宮に還幸
冬 10月12日(壬午) 藤原宮に還った。摂津国造従七位上凡河内忌寸石麻呂、山背国造外従八位上山背忌寸品遲、従八位上難波忌寸浜足、従七位下三宅忌寸大目、4人にそれぞれ位1階を進めた。
還宮。攝津國造從七位上凡河内忌寸石麻呂。山背國造外從八位上山背忌寸品遲。從八位上難波忌寸濱足。從七位下三宅忌寸大目。合四人各進位一階。
国造(くにのみやつこ、こくぞう)とは律令制以前、大和朝廷の時代に地方の豪族に与えられ、その一族に世襲された称号です。天武天皇の時代に国造の制度は廃止されましたが、それ以前から任命されていた国造の地位は据え置きとなり、その1代に限り存続しました。今回の記事にある2人の国造はその「生き残り」であるされています。
律令制が施行されてからも一部の国は例外的に国造が任命されることがありましたが(例えば出雲国造や紀伊国造など)、それ以外の国造の子孫は郡司に任命されるようになりました。
忌寸とは、天武天皇が定めた氏族間の序列制度である「八色の姓」のひとつで、上から4番目のものです。
⭐️八色の姓
真人…最上位の姓。天皇から別れた氏族に与えられた。多治比真人など
朝臣…主に中央の有力氏族に与えられた。藤原朝臣など
宿禰…主に神を祖とする氏族に与えられた。大伴宿禰など
忌寸…国造の一族や渡来系の氏族に与えられた。凡河内忌寸など
道師…授与の実績がなく不明
臣…地方豪族のうち朝臣の姓を与えられなかった氏族か
連…地方豪族のうち宿禰の姓を与えられなかった氏族か
稲置…授与の実績がなく不明

今回4人の位階が昇進されたのは、天皇の行幸にかかわるさまざまなことに従事し貢献したからでしょう。

今の時代でも天皇陛下が行幸されるとなると、大勢の人が動きますからね…今も昔もそこは同じですね。
租庸調の免除
10月15日(乙酉) 行幸に従った諸国の騎兵660人全員に庸調並びに戸の田租を免除した。
從駕諸國騎兵六百六十人。皆免庸調并戸内田租。

騎兵だけで660人とはすごい規模ですね!もしかしたら全体では1000人を超えていたのかも?当時の天皇の行列は私が思っているよりも豪華みたいです✨

古代のことはイメージしづらいですが、具体的な数字があると当時のことが見えてきますね☀️
新羅国王に勅書を賜う

11月3日(癸卯) 新羅国王に次のような勅書を賜った。「天皇、敬いて新羅国王に問う。朕は虚薄(品格、才能に乏しく、浅薄であること)であるにもかかわらず謬りて景運(時の運)により、錬石の才もないままいたずらに握鏡の任(皇位)についていることを慚じている。日が暮れるまで食を忘れ、翼翼の心(畏れ慎む心)は愈積もり、夜更けまで眠ることができない。業業(危ぶみ恐れること)の思いは弥深く、冀わくは覆載(天地や君主の恩恵)の仁を遠く寰区(国の支配領域。天下)に被らし覃ぼすことである。
況や(言うまでもなく)王は世々(代々)国境まで人民を撫で慈しみ、舟を並びつらねて至誠により長く(日本に)朝貢の厚礼を修めてきた。庶わくは、磐石の基を開きて麕(のろじか。小型の鹿で日本にはいない)が棲むような岫を立派な城に固めつくり、芳規(よい決まり)を鴈の棲む池に振い、国内を安楽にし風俗を淳和(すなおで穏やかなこと)ならしめることである。
寒気厳しく、この頃はどうされているだろうか。故に今、大使従五位下美努連浄麻呂、副使従六位下対馬連堅石たちに遣使の意図を申し伝えたので、今これ以上のことを述べることはしない」賜新羅國王勅書曰。天皇敬問新羅國王。朕以虚薄。謬承景運。慚無練石之才。徒奉握鏡之任。日旰忘飡。翼々之懷愈積。宵分輟寢。業業之想弥深。冀覃覆載之仁。遐被寰區之表。
况王世居國境。撫寧人民。深秉並舟之至誠。長脩朝貢之厚礼。庶磐石開基。騰茂響於麕岫。維城作固。振芳規於鴈池。國内安樂。風俗淳和。
寒氣嚴切。比如何也。今故遣大使從五位下美努連淨麻呂。副使從六位下對馬連堅石等。指宣往意。更不多及。
文武天皇は遣新羅使の発遣に先立ち、新羅王(第33代聖徳王)に消息を問う勅書を賜りました。

文武天皇が新羅王に勅書を送るのはこれで3度目になります。
これまで、大宝3年(703)閏4月1日、慶雲3年(706)正月12日の2度送っており、連絡は密で友好的な関係がうかがえます。

勅書の中で語る文武天皇の自身の評価は低いですね。大飢饉や疫病で多くの百姓が死んでいく中、天皇が不徳であると責任を感じていたと思います。

次はどんな神の咎めが起きるのかと、恐ろしくて夜もまともに眠れないというのはあったでしょうね…。当時は夜中ともなれば火灯りくらいでまともに公務が行えたとも思えませんし、精神的な不眠症状で天皇の命を縮めたことは間違いないと思います。
任官(伊勢守)
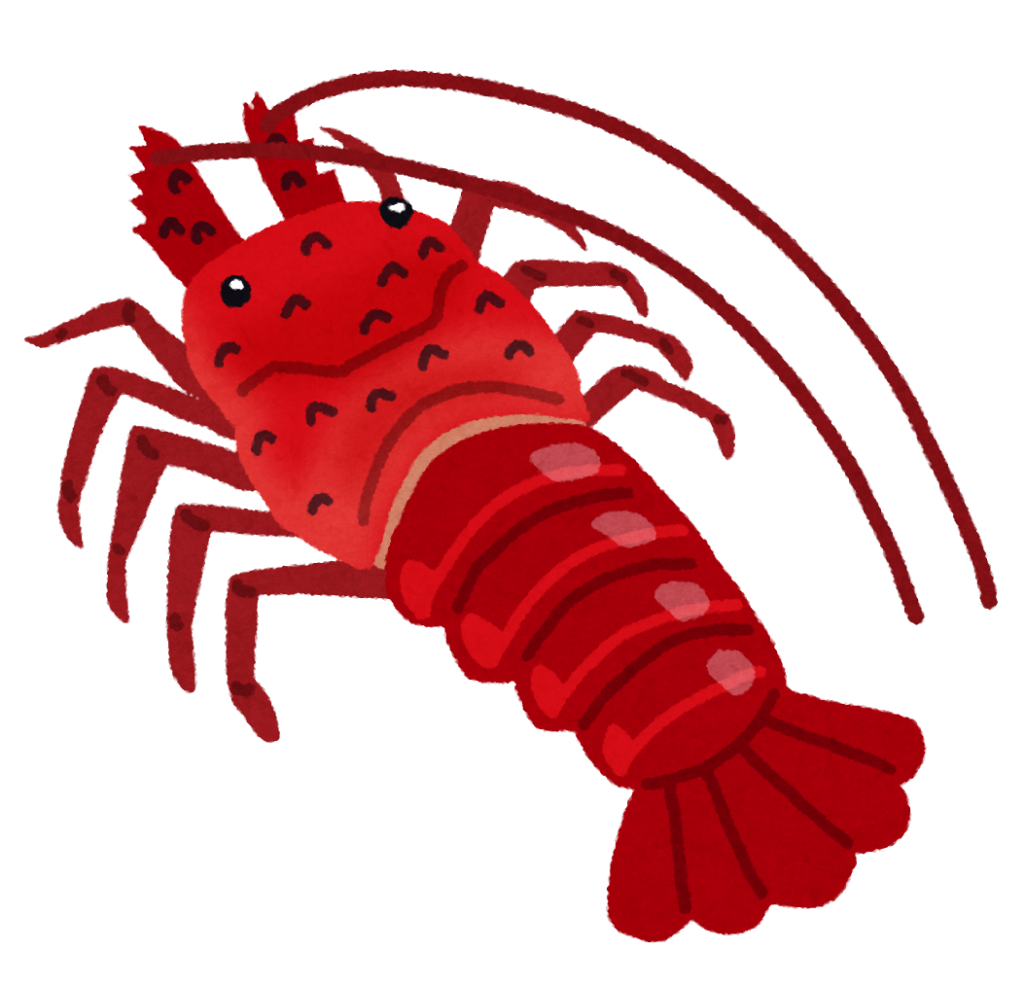
11月8日(戊申) 従五位下大市王を伊勢守に任じた。
從五位下大市王爲伊勢守。
| 国名 | 国力 | 種別 | 守の官位相当 | 主な相当位置 |
| 伊勢国 | 大国 | 東海道 | 従五位上 | 三重県 |
大市王は天武天皇の孫で、父親は長親王です。のちに「文室真人」の氏姓を賜って臣籍に下り、文室¥大市と名乗ります。

ここで問題。大市王は何世の王でしょうか?

天皇の孫だから2世王です!

正解です!皇族の世数の数え方は、天皇を含まず親王を1世として数えます。
日蝕
12月1日(辛未) 日蝕があった。
日有蝕之。
日蝕についてはこちらをご覧ください。
内親王の伊勢参向
12月6日(丙子) 四品多紀内親王を遣わして伊勢大神宮に参向させた。
遣四品多紀内親王。參于伊勢大神宮。
内親王を伊勢に参向させたというのは斎宮になったことを思わせますが、斎宮はこの年の8月29日に新たに田形内親王がその地位についたばかりです。そのため多紀内親王は文字通り伊勢神宮に参向し、何らかの職務についただけであり斎宮になったわけではないでしょう。
多紀内親王の名前は「当耆」または「託基」とも表記し、斎宮の経験者(文武天皇2年(698)9月10日)です。父は天武天皇。

斎宮の経験者として新任斎宮のサポート役を任された…とか?
勅(人民の服装について)
12月9日(己卯) 勅があった。天下の人民に令して、脛裳(くるぶしからすねにかけてを覆う被服。脚半、ゲートル)をやめ白袴を着用させることとした。
有勅。令天下脱脛裳。一著白袴。

白い袴ですか、農作業したらあっという間に真っ黒になりそうですね。こういう人民の衣服って誰がどうやって作ってたんでしょう?政府から支給されたのでしょうか、それとも自前で作ったのでしょうか…
百姓多く死ぬ

この年 天下の諸国に疫疾があり、百姓が多く死んだ。
是年。天下諸國疫疾。百姓多死。
初めて追儺を行う

(続き)
初めて土牛を作って大儺を行った。
始作土牛大儺。
大儺は今でいう節分の行事です。今と違い12月の末に行われ、年の移り変わりに発生するといわれた鬼(ここでは疫病、災害などの邪気をいう)を追い払うため、宮城門の門前で仮面をかぶり鬼に扮した人を追いかける儀式が行われました。追儺ともいいます。
土牛は、平安時代中期の律令の施行細則集『延喜式』によると「12月の大寒の日、諸門に土作りの牛12頭を立てる」とあり、鬼の侵入を防ぐ役割があったのでしょう。

豆まきは!?

追儺の儀式で豆まきが行われるようになったのは平安時代からのようです。
この年、疫病により天下の百姓が多く死んだということで、初めて鬼を払う追儺の儀式が行われたことも、タイミングとして理にかなっている言えます。
次回の記事
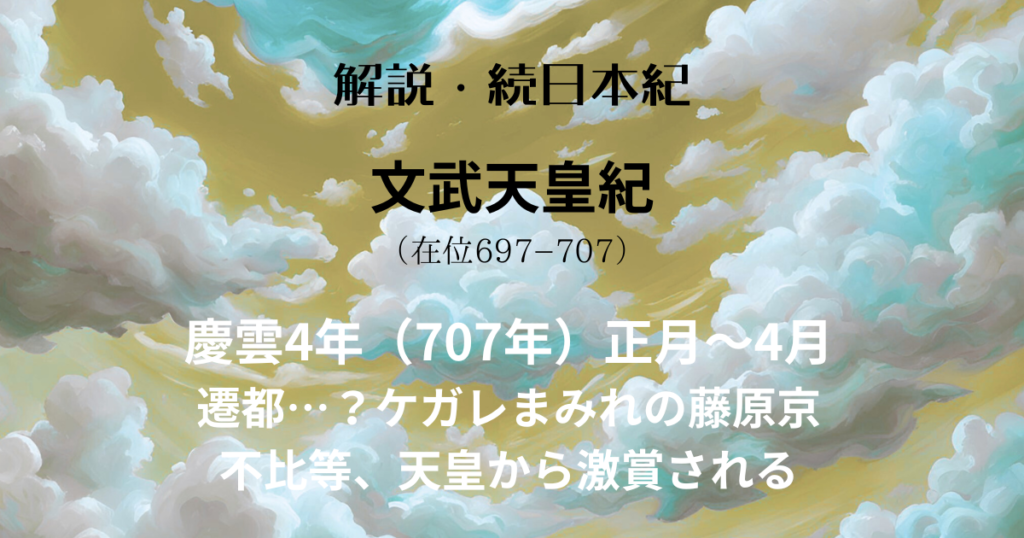

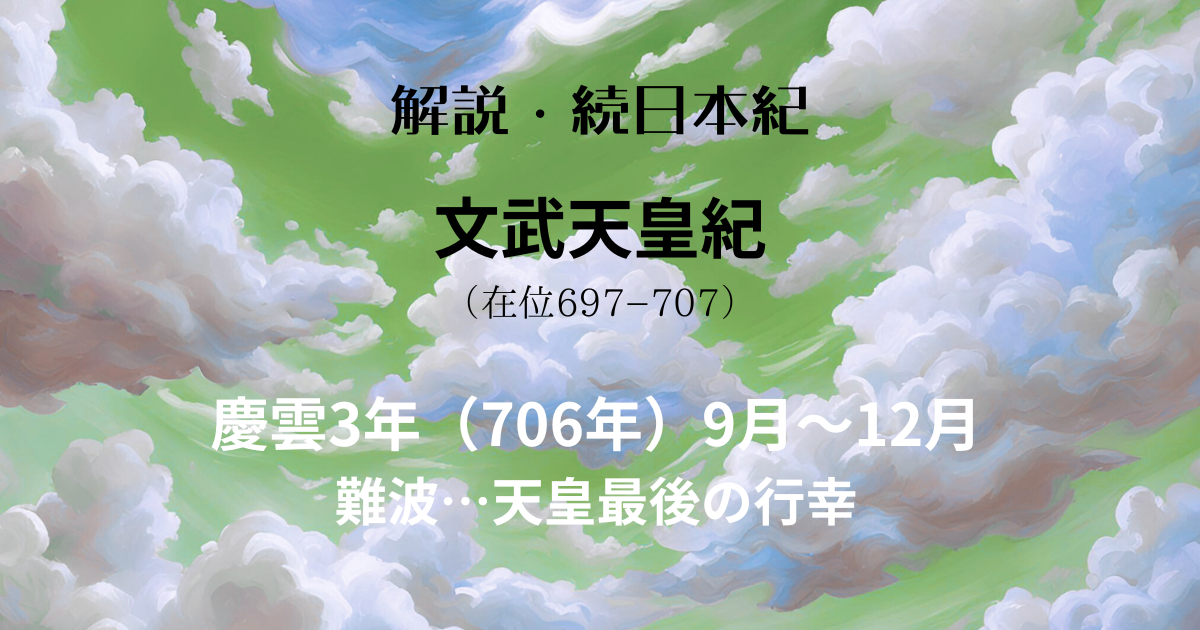

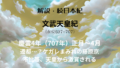
コメント