
こんにちは、みちのくです☀️
今回は『続日本紀』文武天皇の治世元年の記事を取り上げていきます。

即位したての若い天皇の治世ですね🧡
きっと毎日が勉強だったんだろうなぁ…♨️
文武天皇元年(乙酉・西暦697年)現代語訳・解説

食封を賜る
8月29日(壬辰) 王親及び五位以上に、各々差をつけて食封を賜った。
賜王親及五位已上食封各有差。
王親とは皇族のことで、のちの律令においては、「皇親」と呼称されます。五位以上とは貴族のことです。食封とは、給与として領地(封戸という)を与えることをいいます。
「食」の字には「くいぶち」という意味があり、「封」は領地を与えるという意味です。

漢字を分解して意味を調べると分かりやすくなりますね!

封戸を与えられた者は、その土地に住む人民から徴収された稲(租税)の半数と、布などの物品(調)の全部を個人の給与にすることが許されました。
祥瑞の献上
9月3日(丙申) 藤原京の人、
大神大綱造百足の家に嘉稲(めでたい稲)が生えた。近江国(滋賀県)が白い鼈を献上した。
丹波国(京都府中部、兵庫県北東部)が白鹿を献上した。京人大神大網造百足家生嘉稻。近江國獻白鼈。丹波國獻白鹿。
このようなめでたい動物や植物などを「祥瑞」または「瑞祥」といいます。時の天皇が徳をもって良い政治を行うと天を感応させ、それが祥瑞として現れるとされ、改元のきっかけになったりもしました。

祥瑞が現れたことがきっかけで改元することを「祥瑞改元」といいます。

改元の理由としては、今では考えられないですね
叙位(丸部君手)
9月9日(壬寅) 勤大壱(正六位上相当)丸部臣君手に直広壱(正四位下相当)を賜った。壬申の年の功臣である。
賜勤大壹丸部臣君手直廣壹。壬申之功臣也。
蝦夷が産物を献上
10月19日(壬午) 陸奥の蝦夷が貢ぎ物として方物を献上した。
陸奥蝦夷貢方物。
『続日本紀』における蝦夷の初出記事です。
国史における蝦夷の初見は、『日本書紀』の景行天皇27年2月12日(壬子)条。
その記事によると蝦夷は、
「東方にある広大な『日高見国』に棲み、男女とも入れ墨をした蛮族である」
と伝えられています。

東方は陽が昇る方角ですから「日高見国」なんでしょうね☀️

古代の人たちのネーミングセンス、レベル高いですね♨️
朝廷と蝦夷との関係は、手懐けることもあれば、攻撃して征服しようとしたり(逆に蝦夷に反乱を起こされて城が焼かれたりも)、硬軟が混ぜ合わさった対策…いわば飴とムチで保とうとする関係が今後長い間続くことになります。
新羅使の来日

10月28日(辛卯) 新羅使の一吉飡(新羅の官位)金弼徳、副使の奈麻(新羅の官位)金任想らが来朝した。
新羅使一吉飡金弼徳。副使奈麻金任想等來朝。
『続日本紀』にみえる最初の対外記事です。
新羅とは白村江の戦い(663年)など、基本的に日本の敵国でしたが、この時期は国交がひんぱんにありました。もっとも日本は、新羅を「友好国」と見ていたわけではなく、あくまでも貢ぎ物を献上する属国として扱っていました。
新羅使を送迎させる
11月11日(癸卯) 務広肆(従七位下相当)坂本朝臣鹿田、進大壱(大初位上相当)大倭忌寸五百足らを陸路で、務広肆土師宿禰大麻呂、進広参(少初位上)習宜連諸国らを海路にて遣わし、新羅使を筑紫において迎えさせた。
遣務廣肆坂本朝臣鹿田。進大壹大倭忌寸五百足於陸路。務廣肆土師宿祢大麻呂。進廣参習宜連諸國於海路。以迎新羅使于筑紫。
外国からの使者を誰に出迎えさせるかというのは重要な人事です。これを見ると、従七位下や初位といった下級の官人が選ばれているということは興味深いです。
蝦夷に物を賜る
12月18日(庚辰) 越後(北陸の北部地域)の蝦狄に、各々差をつけて物を賜った。
賜越後蝦狄物。各有差。
この頃は、現在の新潟県北部地域はまだ朝廷にとって未開の地であり、統治が行き届いていなかったことが分かります。用字が蝦「夷」ではなく、蝦「狄」となっており、「夷」は太平洋側で、「狄」は日本海側と使い分けがなされています。

もともと「蝦」はカエル、特にヒキガエルを指し、
「狄」はキジ、または「遠い地」を意味する漢字だそうです。

なぜにカエル…?
飢饉の発生
閏12月7日(己亥) 播磨、備前、備中、周防、淡路、讃岐、伊予などの国に飢饉があったので、賑救(財を施し救援)した。
また、負税を徴収することをやめさせた。播磨。備前。備中。周防。淡路。阿波。讃岐。伊豫等國飢。賑給之。又勿收負税。
負税とは、人民に貸し付けた稲のうち返済されていないもののことです。

「閏12月」とは?
2月29日の閏日なら聞いたことありますけど…

これは「閏月」ですね。2〜3年ごとに、12ヶ月に1ヶ月追加して、1年13ヶ月になる年があるんです。

1年が13ヶ月!?
じゃあ閏12月は、「2回目の12月」ってことですか!(驚愕)

はい。当時は月の満ち欠けと太陽の運行を基準に暦が作られていました。
そうすると、月と太陽の周期が少しずつズレていって、暦と実際の季節が合わなくなり農作業などに支障が出てしまうのです。
だから、暦と季節を調和させるため、1ヶ月追加して調整しているのです。
正月拝賀の禁
12月28日(庚申) 正月に人が行き来して拝賀の礼を行うことを禁じた。もし違反者がいれば、浄御原朝廷の制天武天皇が定めた制度により、これを罰することとした。ただし、祖兄及び氏上を拝することは許可した。
禁正月往來行拜賀之礼。如有違犯者。依淨御原朝庭制。决罸之。但聽拜祖父兄及氏上者。
正月とは、1月の全期間のことをいいますが、この記事の場合は元日を意味していると考えられます。祖兄とは親・祖父母・兄などの年長者です。氏上とは藤原氏・蘇我氏・大伴氏など、それぞれの一族をとりまとめるリーダーのことです。
のちに定められる律令には、以下のように規定されています。
律令 巻第7 儀制令(元日条)
元日には、親王以下を拝することを得じ。ただし、親戚及び家令以下は、この限りにあらず。(以下略)
当時は厳格な身分制社会ですから、身分の上の者が下の者に対して拝礼を強要するという実態があったのかもしれません。上下の秩序を保つため、国が「親王以下には拝礼するな」と公に命令したのですね。
参考書籍など
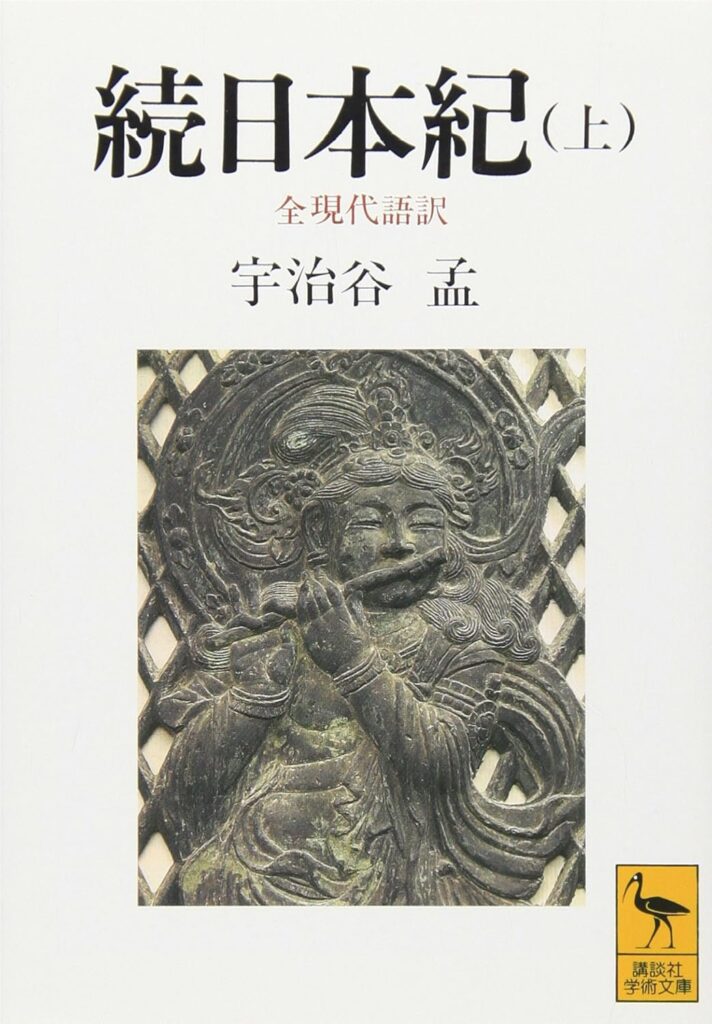
次回予告

文武天皇2年(698年)正月から2月3日までをとりあげます。

↓のバナーから記事に飛べます!ぜひどうぞ♨️↓
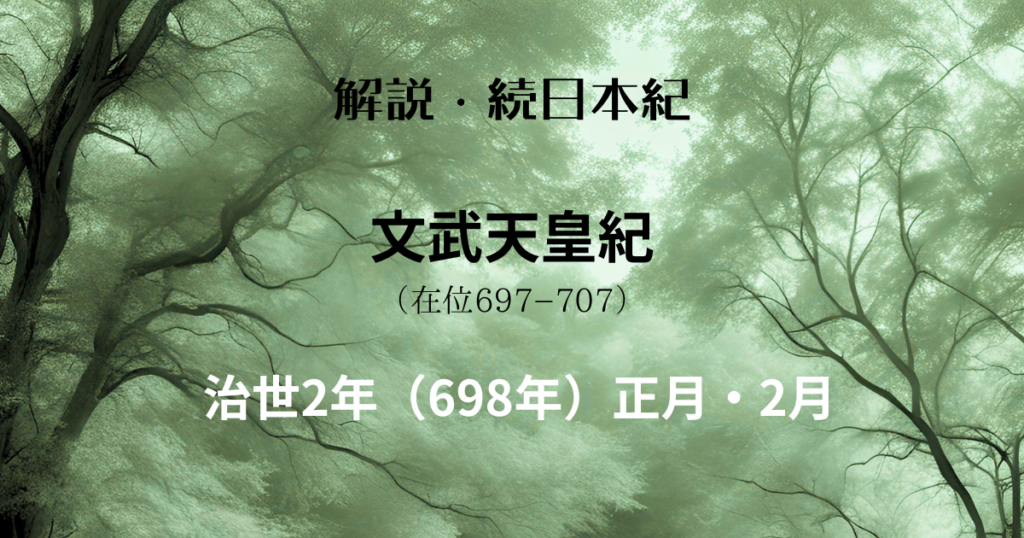

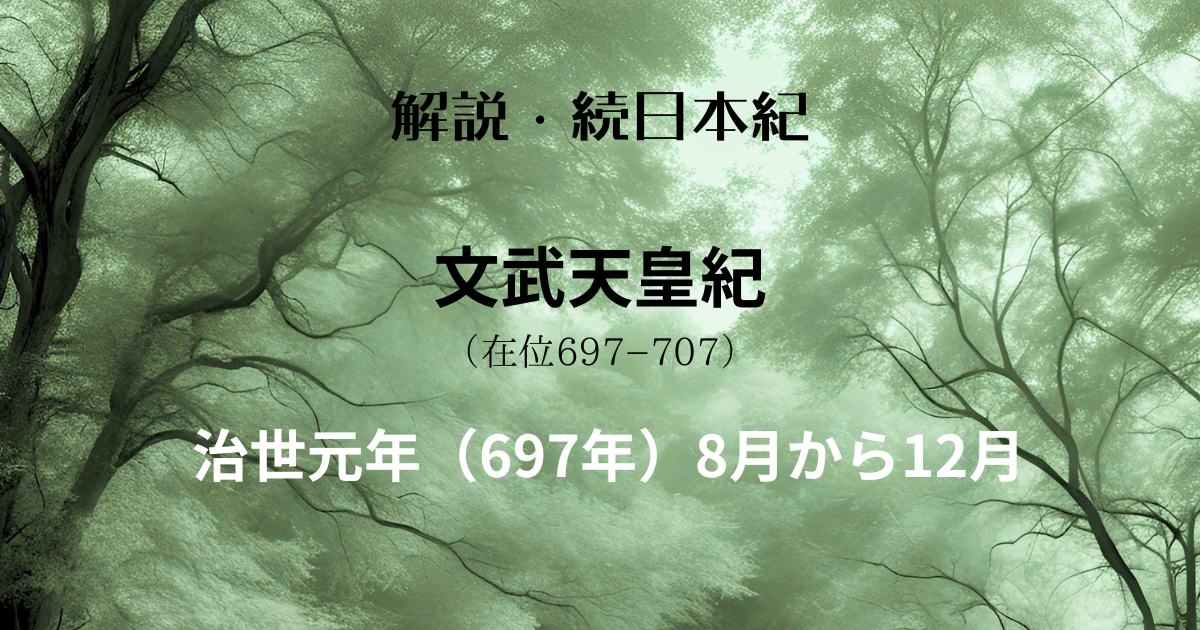

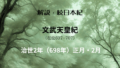
コメント