
こんにちは、みちのくです☀️
今回で和銅2年紀はラストになります。

遷都に関わる記事が多く、平城への行幸もありますね。
天皇の心中はおそらく新都のことでいっぱいになっているようです。
和銅2年(己酉・西暦709年)現代語訳・解説
日蝕
冬 10月1日(癸未) 日蝕があった。
日有蝕之。
日蝕についてはこちらをご覧ください。
考査書類の処理手続きについて
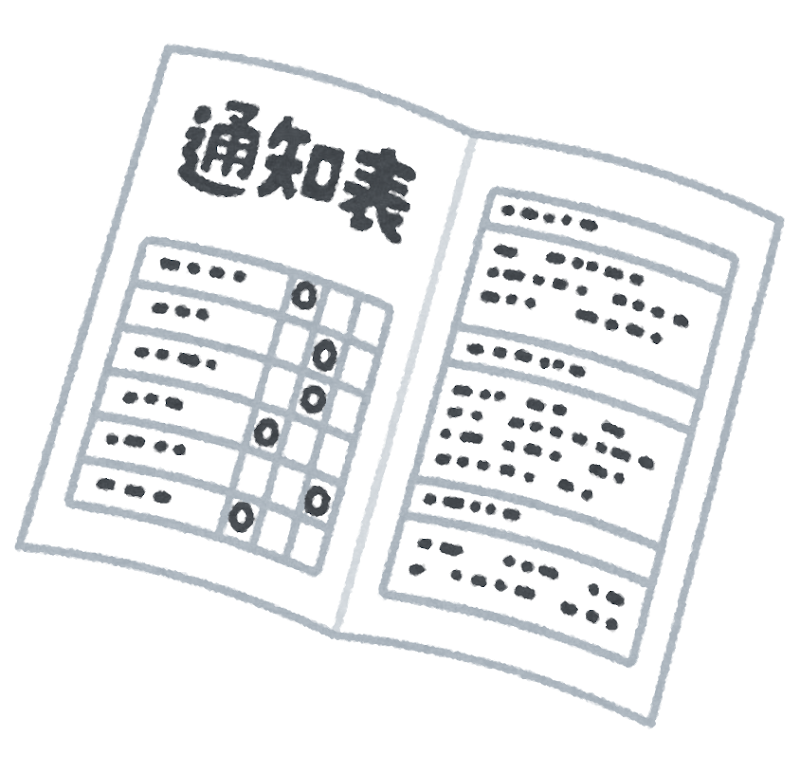
10月2日(甲申) 次のように制定した。「すべての官司の考選の文書(官人の昇進にかかわる勤務評定書)は、まず弁官に提出し、処理が終わったあとに本司に返却し、それから当該官司が式部省または兵部省に申し送るようにすること」と。
制。凡内外諸司考選文。先進弁官。處分之訖。還附本司。便令申送式部兵部。
考選の制度についてはこちらの記事に詳しいです。
弁官は太政官に所属し、太政官と八省の下にある諸官司の間で交わされる行政文書の処理を行った機関です。「式部省または兵部省」とあるのは、文官の人事は式部省、武官の人事は兵部省が司ったためです。
備後国品遅郡の一部を葦田郡甲努村に編入

10月8日(庚申) 備後国葦田郡甲努村は郡家(郡司が政務を執る役所)を去ること山谷が険しい上に遠く隔たっており、百姓の往還に煩費(わずらわしい出費)がはなはだ多い。よって、品遅郡の3里(ここでは距離ではなく、村里の数)を分割して葦田郡甲努村につけることとする。
備後國葦田郡甲努村。相去郡家。山谷阻遠。百姓往還。煩費太多。仍割品遲郡三里。隷葦田郡。建郡於甲努村。
『続日本紀』では説明されていませんが、このとき葦田郡の南に位置する品遅郡(広島県福山市の一部。品治とも書く)の3箇所の里を統合して新たに甲努郡が建てられたようです。

この部分の説明がなければ意味が分からない記事です。
葦田郡の役所が甲努村から遠く不便なので、南隣の品遅郡の3里を分割して甲努郡を新設したということです。

甲奴村の近くに新たに郡司の役所を立てたんですね✨
甲努は「甲奴」とも書かれ、現在でも現地には甲奴の地名が残っています。
甲奴駅ほか周辺には甲奴町の地名がある

山陰、山陽地方と呼ばれることから分かるように、本当に山が多く平地がほとんどないんですね。当時の人が歩くことに慣れてるとはいえ、役所に行くのにいくつもの山道を徒歩で越えなければならないのは今の私たちには想像もつきません。
勅(新京内で墳墓が発掘された場合の措置について)

10月11日(癸巳) 造平城宮司に次のように勅した。「もし、墳壠(墳墓、古墳、埋葬墓)を発掘した場合は、再び埋歛(埋葬し収めること)し、そのまま露にしたまま放置してはならない。すべてこれを祭り、土に酒を注いで幽魂を慰めるようにすること」と。
勅造平城京司。若彼墳隴。見發堀者。隨即埋斂。勿使露棄。普加祭酹。以慰幽魂。
造平城宮司は前年9月30日(戊子)に設置された官司です。その名の通り平城宮の造営を担当した役所ですが、同時に存在した造宮省との関係性はよく分かりません。ただ、この年の9月2日(乙卯)条に見えるように、造宮大丞(造宮省のナンバー3)であり宮殿造りに長けた氏族(台氏)への昇叙が行われていることから、造宮省は平城宮の中枢部の造営を担当し、造平城宮司はより広範囲に建つ官庁などの造営を担当していたのではないかと推測できます。

造宮省ではなく、造平城宮司に対して勅が下された理由を考えると謎が解けそうですね。造平城宮司が担当するエリアに墓や遺骸が発掘されるケースが多かったということですから…。
逃亡の仕丁と、これを匿う罪について
10月14日(丙申) 太政官は次のように禁制した。「畿内及び近江国(滋賀県)の百姓は法律を畏れず浮浪、または逃亡の仕丁(徴集され、公的な労働に従事する成年男子)を容隠(罪人の罪を見逃すこと。罪人を匿うこと)し、私的に使役している。これにより、多くの仕丁がその場所に住みつき、本籍地に帰っていない。これは百姓ただひとりの違法というものではなく、国司が懲粛(こらしめ戒めること)を加えていないということであり、公私を蠹害(物事を害すること)することこの上ない有様である。今後はこのようなことがあってはならない。
禁制。畿内及近江國百姓。不畏法律。容隱浮浪及逃亡仕丁等。私以駈使。由是多在彼。不還本郷本主。非獨百姓違慢法令。亦是國司不加懲肅。害蠧公私。莫過斯弊。自今以後。不得更然。
律令制は人民を戸籍により把握し、それをもとに班田を行い租を徴収。その他庸・調の物品の貢納や肉体労働などを行う義務がありますが、今回は仕丁として労働に徴集された人が逃亡し、他の百姓の戸に隠れて匿ってもらうというケースが多発しているということです。

ここでのポイントは、問題視されているのが逃亡した仕丁やこれを匿った百姓ではなく、この状況を引き起こした国司であるということです。

国司は人民を管理する義務と責任があるという事ですね。
(続き)
国司は国内の担当者に暁示(諭すこと)して取り締まりを行わせ、その結果を11月30日までに申告させるようにせよ。この太政官符が到着してから5日以内に、逃亡罪と隠蔵罪(逃亡者を匿う罪)とを問わず、並びに全て自首させること。この期限内に自首しなかった者は律により科罪する。もし事情を知りながらあえて逃亡者を匿っていた者があれば、逃亡者と同罪とし、官当(官人が官位剥奪と引き換えに実刑を免除される制度)、蔭贖(親が位階を有している者が、銅などの物納により刑を免除される制度)を得ることはできない。国司がこれを糺さないときは法により科罪する」と。
宜令曉示所部検括。十一月卅日使盡。仍即申報。符到五日内。无問逃亡隱藏。並令自首。限外不首。依律科罪。若有知情故隱。与逃亡同罪。不得官當蔭贖。國司不糺者。依法科附。


自首は認められるんですね。自首をしたら罪を許されるのでしょうか…?

この文脈だとおそらく許されるのではないでしょうか。律には自首についての規定があり、比較的軽い罪は減刑や刑を免除されるようです。

ちなみに律令には防人(国土防衛の兵士)や衛士(門番)、仕丁など、公の労働に従事する者が逃亡した場合に、これを捕らえることを規定した条文が存在します。
律令 捕亡令 第1(囚及征人条)
すべて囚人及び征人(征討に徴発された人)、防人、衛士、仕丁、流移(流は流罪となった人。移は死罪を許された人が郷里を移され別の場所に移送されること)の人が逃亡したときは、その付近の官司に届け出ること。届出を受けた官司はその逃亡者の住居、所属及び国司・郡司に告知してこれを追捕すること。告知を受けたところは、逃亡者の郷里の四隣五保(近隣の5戸を単位に構成された地域の共同体(保)で、行動を互いに監察する義務がある)に命じて捜索させ、捕らえさせるようにすること。

太政官が禁制を出すまでもなく、もともとこういう規定があったんですね。実態はあまり機能していなくて野放しになっていたということなんでしょうか?
薩摩隼人の入朝

10月26日(戊申) 薩摩(鹿児島県西半部)の隼人、郡司以下188人が入朝した。諸国の騎兵500人を徴兵して威儀の列を備えた。
薩摩隼人郡司已下一百八十八人入朝。徴諸國騎兵五百人。以備威儀也。
隼人は南九州に居住しており、朝廷への服属が遅れたために辺境の異民族として扱われる一方、不思議な呪力を持つ存在として中央から畏敬の念を抱かれていました。
今回の記事は、薩摩の郡司が隼人180人余りを引率して入朝したという意味でしょう。郡名が書かれていないため、複数の郡司が共同で移動してきたのかもしれません。

『日本書紀』神代・下によると、隼人の一族は天皇と祖先を同じくしています。
元日の朝賀など重要な儀式があるときは↑にあるような特有の渦巻き紋様が描かれた楯が立てられ、吠声という犬の吠え声を発して邪を払ったといわれています。

東北や北陸の蝦夷とは違って、同じ辺境の蛮族であっても隼人は神聖視される存在だったようですね。

はい、しかしその一方で隼人と朝廷は服属を巡って敵対することも多かったです。蝦夷ほど対立が長期化することはなかったようですが、以下のような反乱がありました。
大宝2年(702)8月1日(甲申) 多褹(種子島)の隼人が反乱し、征討軍が組織され鎮圧される。
養老4年(720)2月29日 大隅国(鹿児島県東半部)の隼人が反乱し、6月17日に鎮圧される。

今回騎兵500人でもって威儀を備えたというのも、隼人への畏敬の念の表れでもあり、整った軍事力を示して上下関係を知らしめる意図もありそうですね。
詔(遷都で動揺する百姓に租調を免除)
10月28日(庚戌) 次のように詔した。「このところ、遷都により住む土地が変わる百姓の間に動揺が広がっている。鎮撫を加えているとはいえ、未だに安堵することができないでいるようである。これを思うたびに、朕は甚だ憐れんでいる。よって、当年の調・租を全て免除すること」と。
詔曰。比者。遷都易邑。搖動百姓。雖加鎭撫。未能安堵。毎念於此。朕甚愍焉。宜當年調租並悉免之。
つい10月14日に畿内と近江国の逃亡・浮浪の百姓を匿っている者の取り締まりを行うよう指令が下っていますが、平城京造営の負担から逃れるために逃亡した人も多かったのではないでしょうか。

遷都と新しい京の造営が庶民にどれほどの体力的・精神的負担が強いていたかがよく分かりますね。

このときの京は飛鳥にある藤原京。造営が持統天皇8年(694)のことなので、15年間の京だったわけです。これまでにも天皇の代が代われば遷都は行われてきましたが、その度に新しい都城をつくるとなると庶民が辟易するのも自然ですね。
任官(宮内卿、右兵衛率、国守)
11月2日(甲寅) 従三位長屋王を宮内卿に任じた。
以從三位長屋王爲宮内卿。
長屋王

長屋王はのちに謀反の罪を着せられて死を賜ることになる長屋王の変(神亀6年・729)で著名な人物です。天武天皇の孫であり、父は天武の長子・高市皇子、母は天智天皇の皇女・御名部皇女。

長屋王の史料上の初見はこちら(慶雲元年(704)正月7日条)。
20歳ころの長屋王は律令の規定を無視した、無位から一挙に正四位上へ出世するという異常とも言える高待遇を受けています。

両親ともに皇族で、父は天武天皇の長男、母は天智天皇の皇女…。この上ないほど高貴な出自ですね。政変までまだ20年もありますが、20代半ばにしてすでに従三位宮内卿という高位に…!
ちなみに、前任の宮内卿は犬上王という皇族でしたが、この年の6月28日(癸丑)に死去しており空席となっていました。
それぞれの前任者
(続き)
従五位上田口朝臣益人を右兵衛率(右兵衛府の長官)に任じた。
従五位下高向朝臣色夫智を山背守に、従五位下平群朝臣安麻呂を上野守に、従五位下金上元(金上无か)を伯耆守に、正五位下阿倍朝臣広庭を伊予守に任じた。從五位上田口朝臣益人爲右兵衛率。
從五位下高向朝臣色夫智爲山背守。從五位下平羣朝臣安麻呂爲上野守。從五位下金上元爲伯耆守。正五位下阿倍朝臣廣庭爲伊豫守。
今回任官があった官職の前任者は、それぞれ以下の通りです。
・右兵衛率 従五位下高向朝臣色夫知
・山背守 従五位下坂合部宿禰三田麻呂
・上野守 従五位上田口朝臣益人
・伯耆守 不明
・伊予守 従五位上久米朝臣尾張麻呂
伯耆守に任じられた金上元は、和銅元年(708)正月11日条に名前が見える、和銅の発見の功績により無位から従五位下に叙された金上无ではないかと思います(元と无の文字誤り?)。

国守に抜擢されるなんて、出世しましたね
平城宮に行幸

12月5日(丁亥) 車駕(天皇の乗る御車。転じて天皇自身を指す。しゃが)が平城宮に行幸した。
車駕幸平城宮。
8月28日(辛亥)の平城宮行幸に続き、わずか3ヶ月ぶりに再び同地への行幸が行われました。今回の行幸については、どのような活動があったのか記述がまったくないため不明です。いつ藤原京に帰ってきたのかも分かりませんが、年明けの正月1日には朝賀の儀式が行われているため、年内には還幸されたようです。

ともかくも、遷都を直前に控えて元明天皇の新都に対する熱量と「はやる心」を強く感じますね。

とはいえ旧暦の12月上旬は今の1月下旬ごろなので、1年で最も冷え込む時期です。行幸をするのも大変だったことでしょう。
卒(下毛野古麻呂)
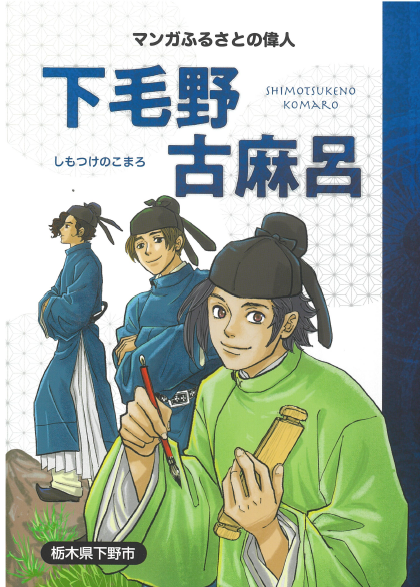
12月20日(壬寅) 式部卿大将軍正四位下下毛野朝臣古麻呂が卒した。
式部卿大将軍正四位下下毛野朝臣古麻呂卒。
事績について

下毛野古麻呂は『日本書紀』『続日本紀』に名前が多く残る人物です。特に『続紀』は豊富で、これまでの事績は以下のようになっています。
⭐️日本書紀
持統天皇3年(689)10月22日(辛未) 直広肆(従五位下相当) 奴婢600人を放免したいと奏上し、許される。
⭐️続日本紀
文武天皇4年(700)6月17日(甲午) 直広参(正五位下相当) 大宝律令撰者として禄を賜る。
大宝元年(701)8月3日(癸卯) 従四位下 大宝律令完成により禄を賜る。
大宝2年(702)5月21日(丁亥) 参議に任じられる。
大宝3年(703)2月15日(丁未) 詔により、大宝律令撰定の功績により田10町、封50戸を賜る。
同年3月7日(戊辰) 功田20町を賜る。
慶雲2年(705)4月22日(辛未) 兵部卿に任じられる。
慶雲4年(707)3月22日(庚申) 従弟の石代の姓を「下毛野河内朝臣」に改めることを要請し、許可される。
同年10月3日(丁卯) 文武天皇の造山陵司に任じられる。
和銅元年(708)3月13日(丙午) 式部卿に任じられる。
同年7月15日(乙巳) 天皇の御前に召され、勅により他8人の高官とともに働きぶりを褒められる。
大将軍とは?
記事中、「式部卿大将軍正四位下」とありますが『続日本紀』では、大将軍にいつ任じられたのかは記述がなく不明です(正四位下の叙任時期も同じく不明)。ただし10世紀後半に成立したといわれる朝廷の歴代高官を列挙した『公卿補任』によると、和銅元年7月1日に任じられたとのことです。
この突然出てきた「大将軍」ですが、律令の「軍防令」に以下のようにあります。
律令 軍防令 第24(将帥出征条)
将軍が征討に出るときは、兵1万人以上であれば将軍1人、副将軍2人、軍監2人、軍曹4人、録事4人とする。兵5千人以上であれば将軍1人、副将軍1人、軍監1人、軍曹4人、録事2人とする。3千人以上であれば将軍1人、副将軍1人、軍監1人、軍曹2人、録事2人とする。これらをそれぞれ(編成の単位として)一軍とせよ。三軍を統べるごとに、大将軍1人を置く。
つまり大将軍は、三軍とこれを率いる将軍3人を統括する総司令官的な役割だったということです。『公卿補任』によると下毛野古麻呂は和銅元年7月1日に大将軍に任じられたわけですが、その翌年に越後国(出羽郡)と陸奥国の蝦夷征討軍が編成されています(こちらを参照)。そのため、古麻呂は蝦夷征討軍の総司令官だったのではないでしょうか。

しかし、古麻呂が大将軍として征討を指揮したといった記事は全くなく、他の将軍と副将軍が戦地から凱旋したときに天皇から戦果を讃えられた(こちらを参照)にもかかわらず、大将軍古麻呂の名前は一切出てきません。
また、征討軍編成のため各国(遠江、駿河、信濃、甲斐、上野、越前、越中)から徴兵が行われましたが、下毛野氏の本拠である下野国からは徴兵の記録がありません。このことから、古麻呂は大将軍でありながら蝦夷征討に反対していた可能性がありそうです。

大将軍であるからには、自分の本拠から兵を出すはずですよね。
それにしても反対の立場なのに大将軍を任されるというのも、すごいですね。

古麻呂は軍団を動かす兵部卿の経歴がありますし、東国の地理にも詳しい上に天皇から名指しで優秀であると褒められるほどですからね。大将軍の適任者は彼しかいないとなったのかも。

とはいえこれでは大将軍の名前も完全に宙に浮いてますね…
続日本紀 巻第4 終
次回の記事
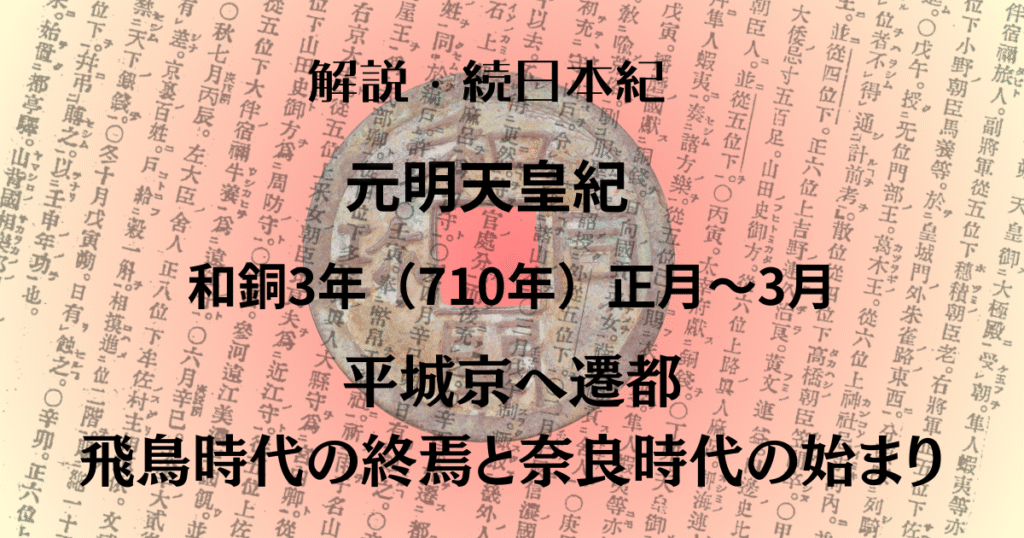

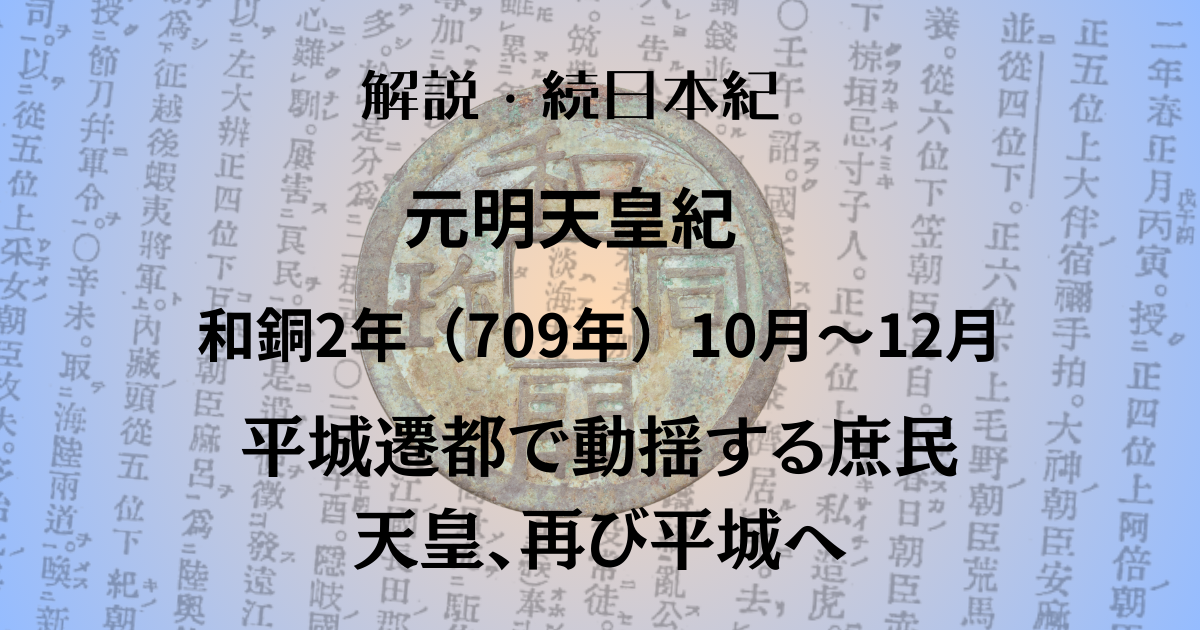
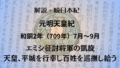
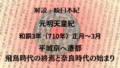
コメント