
こんにちは、みちのくです☀️
今回は文武天皇治世2年2月から3月までの記事を紹介していくよ。

よろしくお願いします♨️
文武天皇2年(西暦698年)現代語訳&解説
宇智行幸

2月5日(丙申) 車駕。は、宇智郡に行幸した。
車駕幸宇智郡。
宇智郡は、大和国(今の奈良県五條市)にあった郡です。宇智について『万葉集』に、次の歌が収められています。
『万葉集』巻第1 歌番号:4
天皇が宇智の野に遊猟された時に、中皇命 が 間人連老に奉らせたまう歌
たまきはる 宇智の大野に 馬並めて 朝踏ますらむ その草深野
(現代語訳)
魂のきわまる宇智の大野に馬をつらね、朝には大地を踏ませていることだろう、その草深い野で

「たまきはる」とは「宇智」にかかる枕詞ですね。
「魂のきわまる」宇智ってそんなに血湧き肉踊るところだったのでしょうか?

狩りといえば「宇智」だったのかもしれません。
だからこそ「たまきはる」のでしょう。
宇智には「大野」があり、狩りに適した地だったことが分かります。この歌にいう「天皇」は文武天皇のことではなく、文武の曽祖父・第34代舒明天皇です。が、文武天皇も訪れた宇智の大野で狩りをされたのかもしれません。

見晴らしの良い丘から宇智の平原を見下ろす馬上の文武天皇…。
りりしい横顔をイメージするとほれぼれしちゃいます!✨

文武天皇はその伝記から、弓術が得意だったそうです。
そういう景色は当時本当にあったかもしれません!✨
現在宇智は、郡としての名前は消滅しましたが、宇智神社、宇智川などに地名が残っています。

禄を賜う(職事以上、才伎の長上)
2月12日(癸卯) 百官の職事以上と、才伎の長上に各々差をつけて禄を賜った。
賜百官職事已上及才伎長上祿各有差。
諸々の役所のうち、位階を有し律令法典に規定された官(職事官)と、特殊な技能を持つ者(才伎)のうち常勤で勤務している者(長上)それぞれに禄(給料)を賜ったという意味です。

常勤の人を「長上」といい、非常勤の人を「番上」といいます。

どれも今では使われていない言葉なので難しいですね💦
禄を賜う(武官)
2月15日(丙午) 各々差をつけて武官に禄を賜った。
賜武官祿各有差。
銅鉱石の献上、疫病の発生
3月5日(乙丑) 因幡国(鳥取県東半部)が銅鉱を献上した。
因幡國獻銅鑛
銅鉱とは、銅を含んだ鉱物であり純粋な銅になる前の状態を指しています。つまり因幡国では銅山があるということで、この記事は日本の記録にあらわれる最古の銅山ということになります。今では銅は採掘されていませんが、戦後まもなく閉山されるまで銅の大きな産地となりました。
疫病の発生
3月7日(丁卯) 越後国(新潟県)が疫病の発生を言上(報告)してきたため、薬を賜い、これを救わせた。
越後國言疫。給醫藥救之。
詔(郡司の任命について)
3月9日(己巳) 次のように詔した。「筑前国宗形郡(福岡県宗像市)と出雲国意宇郡(島根県出雲市・松江市)の郡司は、これを任命するときに三等以上の親族の任命を許すこと」と。
詔。筑前國宗形。出雲國意宇二郡司。並聽連任三等已上親。
郡司とは、郡の行政をつかさどった地方官で、当地の豪族(勢いのある有力者、実力者)が任命されました。この2つの郡の共通点は、宗像大社・出雲大社・熊野大社という特別に格の高い神社の所在地であるということです。こういった大きく格式の高い神社を擁する郡のことを神郡といいます。
もともと、郡司は当地の有力者一族が世襲により任命されていました。が、今回の詔により、この2つの神郡については、神社を代々継承する一族(宗像氏、出雲氏)から3親等以上の親族(4親等や5親等)までの任命を特別に認めたのです。

これはどういう意図があったと思いますか?

神社の神職は、特に血統による継承が必要な職ですから、神郡については親族から任命する郡司の範囲を特例で拡大したのだと思います。
詔(国司と郡司に規律と法の遵守を求める)
3月10日(庚午) 諸国の郡司を任命した。よって次のように詔した。「諸国の国司らは郡司を詮議(評議して物事を決めること)するにあたっては偏党(一定の立場や思想に偏ること)があってはならず、郡司もその任にあるときは必ず法に従わなければならない。今後はこれに違反があってはならない。」と。
任諸國郡司。因詔諸國司等銓擬郡司。勿有偏黨。郡司居任。必須如法。自今以後不違越。
参考書籍など
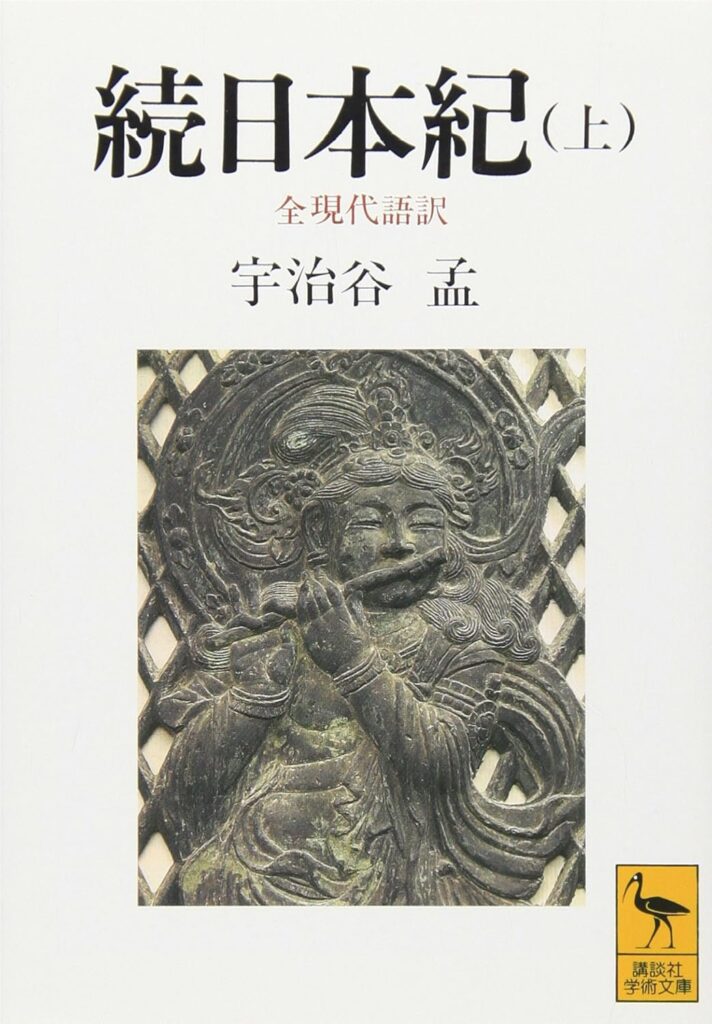
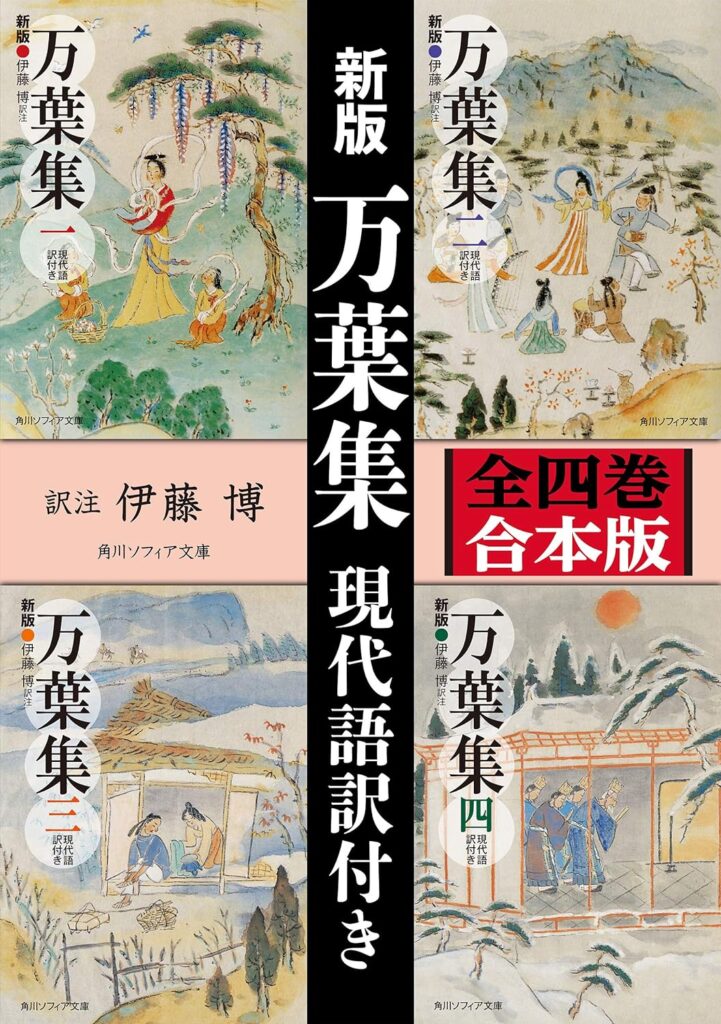
次回予告

次回は文武天皇治世2年、3月から5月までの記事ついてとりあげます☀️

↓のバナーから飛べます、ぜひ見てみてくださいね♨️
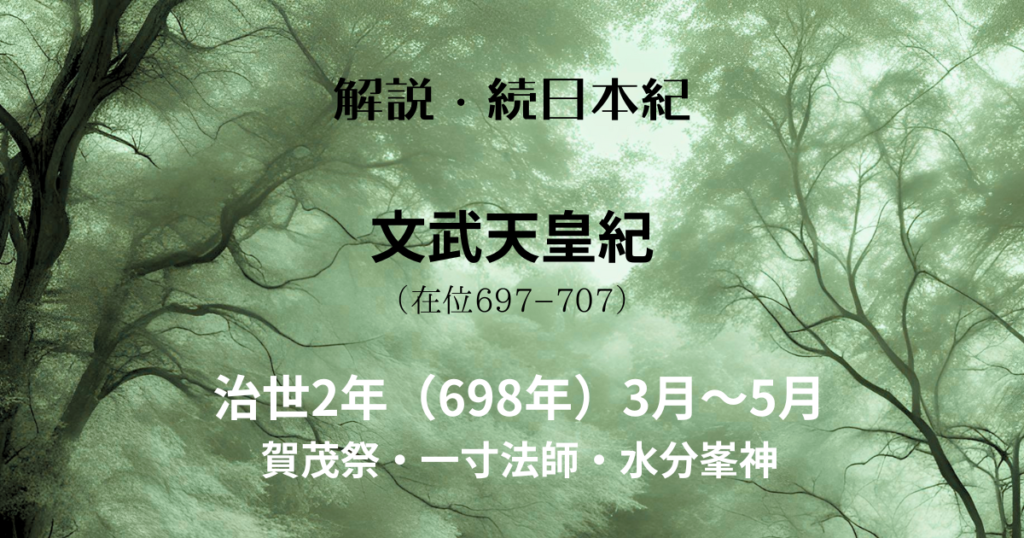

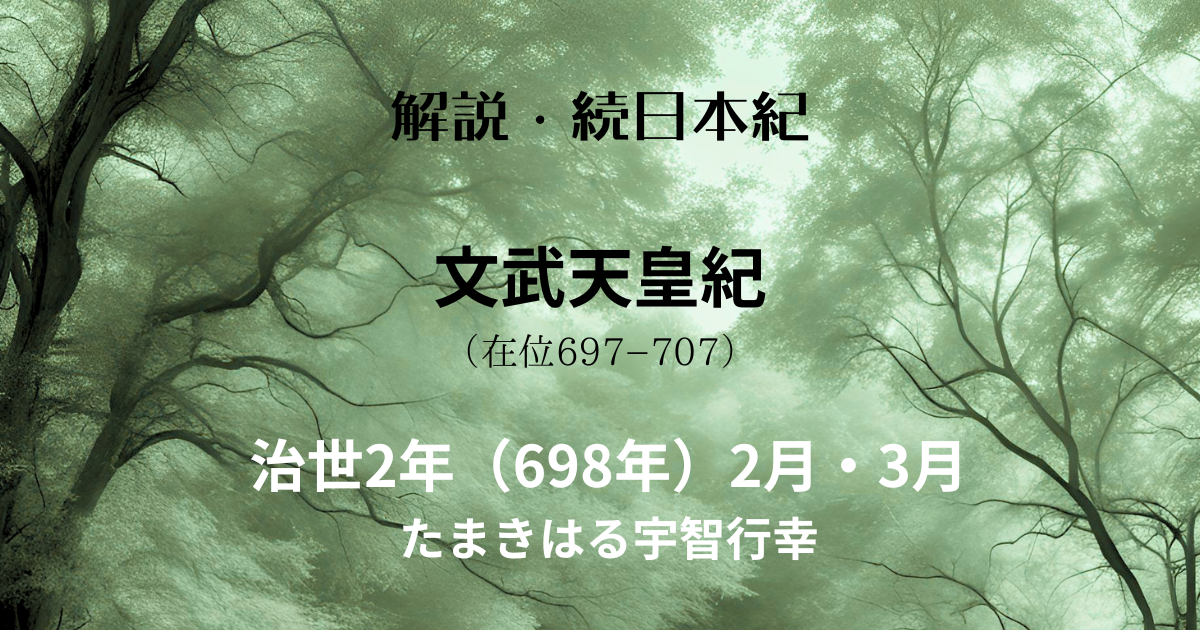
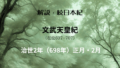
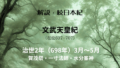
コメント