
こんにちは、みちのくです☀️
『続日本紀』大宝元年(701)3月から6月までの記事を解説していきます。
今回は古代で使われていた単位や、競馬(くらべうま)や遣唐使の話などが出てきます!

よろしくお願いします♨️
大宝元年(西暦701年)現代語訳・解説

丹波国で地震
3月26日(己亥) 丹波国(京都府・兵庫県)に地震があり、3日間続いた。
丹波國地震三日。
右大臣阿倍御主人への贈賜、古代で使われていた単位について
3月29日(壬寅) 右大臣従二位阿倍朝臣御主人に絁500疋、糸400絇、布5,000段、鍬1万口、鉄5万斤、備前(岡山県西部)・備中(岡山県東南部)・但馬(兵庫県)・安芸国(広島県)の田20町を賜った。
賜右大臣從二位阿倍朝臣御主人。絁五百疋。絲四百絇。布五千段。鍬一万口。鐵五万斤。備前。備中。但馬。安藝國田廿町。

見慣れない単位がいくつか出てきたので以下にまとめます。
⭐️単位について
疋 絁(目の粗い絹)や絹などの枚数。「匹」とも表記される。
段 布の枚数。布の場合は普通「端」と表記される。
絇 生糸の重さ。律令時代の基準では1絇はおよそ600グラム。600グラムは蚕の繭1,200〜2,000個分から生成される糸に相当する重さ。
斤 重さを示すときの汎用単位。律令次代の基準では1斤はおよそ600グラム。
口 物を個数を数えるときの汎用単位(「個」に近い)。金属具、刃物などを数えるときに使われることが多い。また、人の数を数えるときにも使用されることがある。
町 距離や面積の単位。今回は田の面積を示し、律令制における1町はおよそ11,900㎡(≒1.19ha)。


長さや重さなどの単位は大宝令や大化の改新の詔で定められました。
ですが、現在では使われない単位が多い上に、時代により同じ単位でもその値が異なる場合もあるので、少々やっかいです。
長さの単位としては、丈・尺・寸・分があります。1尺は1丈の1/10、1寸は1尺の1/10、1分は1寸の1/10です。平城宮から出土した竹定規によると、1尺は29.6cmであることが判明しています。よって、1丈は296cm、1寸は2.96cm、1分は0.296cm(約3mm)となります。


定規が出土!これで今の単位に換算できるわけですね✨

ちなみに、大化2年「改新の詔」第4条によると、1疋、すなわち絁や絹1枚の規格サイズは「4丈×2尺半」と定められており、長さ1184cm×幅74cmの長方形になります。面積で言うと、およそ8.7㎡になりますね。

ということは右大臣が賜った絁500疋は、8.7㎡×500=4,350㎡…。

面積4,350㎡は大体サッカーコート半面とちょっとくらいの規模感。この量の絁を下賜されるとは、さすが右大臣といえますね。
日蝕

夏 4月1日(甲辰) 日蝕があった。
日有蝕之。
日蝕については、こちらをご覧ください。NASAによると今回の日蝕は部分日食でした。しかし発生時の日本は夜の時間帯にあたるため当時観測することは不可能だったようです。
勅(中臣氏に奉斎神稲支給)
4月3日(丙午) 勅があった。山背国葛野郡(京都市域)月読神・樺井神・木嶋神・波都賀志神に奉納する神稲は、今後は中臣氏に給うこととする。
勅。山背國葛野郡月讀神。樺井神。木嶋神。波都賀志神等神稻。自今以後。給中臣氏。
「中臣氏に給う」というのは、中臣氏にこれらの神の祭りを行わせるという意味です。
波都賀志神は、現在京都市伏見区に「羽束師坐高御産日神社」に祭られています。
大宝令の講義
4月7日(庚戌) 右大弁従四位下下野朝臣古麻呂たち3人を遣わして初めて新令(大宝令)の講義を行わせた。親王、諸臣百官の人たちがこの教習を受けた。
遣右大弁從四位下下毛野朝臣古麻呂等三人。始講新令。親王諸臣百官人等就而習之。

下野古麻呂は、律令撰定で主要な役割を果たしたメンバーです。
前年(700)6月、律令撰定の功により禄を賜ったとの記事があり、19名中、古麻呂は4番目に記載されています。

まさに律令の専門家と呼ぶに相応しい人選だったわけですね!✨
賜姓(垂水君)
4月10日(癸丑) 遣唐大通事(通訳官のトップ)大津造広人に垂水君の姓を賜った。
遣唐大通事大津造廣人賜垂水君姓。
遣唐使の朝見
4月12日(乙卯) 遣唐使たちが朝廷を拝した。
遣唐使等拜朝。
朝廷を拝したということは、出発の日が近いということです。しかし、風波が荒れたため、結局翌年の6月になるまで唐に向けて出航できなかったようです(大宝2年(702)6月29日条)。

今とは違い、船旅は命懸けです!
田領の廃止
4月15日(戊午) 幣帛を諸社に奉って、名山・大川に祈雨した。
田領を廃止し、国司にまかせて田の経営を巡検させることにした。奉幣帛于諸社。祈雨于名山大川。罷田領委國司巡検。
田領は、『日本書紀』欽明天皇17年7月条に「田令(たつかい)」の語が初めて見え、これと同じものとすると、中央から派遣されて田の経営を監督した職になります。旧制度を廃止し、これも律令制に基づき国司が担当することになりました。
太政官処分
5月1日(癸酉) 太政官は次のように処分した。「王臣(皇族と臣下)のうち、五位以上の者の上日(出勤日)については、月末にその管轄の官司が式部省に送り、その後に式部が書き写したものを太政官に申し送ること」と。
太政官處分。王臣五位已上上日。本司月終移式部。然後式部抄録。申送太政官。
太政官は、国政を統括する朝廷の最高機関です。律令制は二官八省制という、神祇官・太政官の二官と、太政官の下の中務・式部・治部・民部・兵部・刑部・大蔵・宮内の八省により運用されていました。この中の式部省は、官人の名簿・勤怠管理・昇進のこと・位記のこと・学校のことなどを担当しました。
走馬(競馬)の初見
5月5日(丁丑) 群臣の五位以上の者に、走馬を出させ、天皇が臨御してご覧になった。
令群臣五位已上出走馬。天皇臨觀焉。

走馬とは、二頭の馬を騎馬で走らせ順位を争う宮中行事で、競馬(くらべうま)ともいいます。これが史書に現れる競馬の初見です。
延長5年(927)に完成した律令の施行細則『延喜式』によると、この日に官人は全員菖蒲(あやめ、しょうぶ)の葉飾りを冠につけることとされました。

これには主に健康や厄除けの意図があり、菖蒲は古くから「尚武」の意味が込められ、武の精神を表すとされていました。

武を尚ぶ…なんだか菖蒲の花がかっこよく見えてきました!

また、菖蒲は薬草としても知られ、邪気を払う力があると信じられていました。

毎年5月5日は「端午の節会」といい、このような馬術競技を天皇が観覧するという行事が古来から行われていたようです。

今の競馬とは違い、単なる娯楽ではなく武術訓練や神の祭りのために行われた、国の大切な行事だったんですね♨️
第8回遣唐使発遣にかかる節刀の下賜、官人の休暇について
5月7日(乙卯) 遣唐使粟田朝臣真人に節刀を授けた。
次のように勅を下した。「官人の取得する休暇については、一位以下の者は、15日間を限度とする。ただし、大納言以上の者はこの限りでない」と。入唐使粟田朝臣眞人授節刀。勅。一位已下。賜休暇不得過十五日。唯大納言已上。不在聽限。
粟田真人は遣唐執節使という、遣唐使の最高責任者です。執節とは、節を執ることであり、「節」は印(しるし)、「執」は手に取ることを意味します。つまり粟田真人は、天皇の代行者として「節刀」を下賜されたということです。

粟田真人の言葉は天皇のお言葉であるぞ!というわけですね☀️

この節刀が目に入らぬか!というわけですね♨️
以後、征夷大将軍などに節刀が授けられる事例が出てきますが、今回が節刀下賜の史料上の初見です。

ちなみに、今回の遣唐使発遣は8回目となり、前回から30年の年月が経過していました。大宝律令完成は、日本が国家としての体裁を整えたということですから、これを大陸に知らしめるという意義がありました。
日本という国号を体外的に示したことも今回が初めてとされています!

ついに日本も「倭国」を脱却したんですね!✨
冠位から位階へ名称を改める
5月27日(己亥) 初めて勤位以下の名称を改めて、六位以下の者の階を一級進めた。
始改勤位已下之号。内外有位六位已下者。進階一級。
道首名に僧尼令の講義を行わせる
6月1日(壬寅) 正七位下道君首名に、大安寺で僧尼令の講義を行わせた。
令正七位下道君首名説僧尼令于大安寺。

下野古麻呂と同じく、道首名も律令撰定のメンバーでした。
正七位下というと、位階としてはかなり下位ですが講義を任される優秀な官人でした。
壬申の乱の褒賞
6月2日(癸卯) 正五位上忌部宿禰色布知が卒した。詔により従四位上を贈った。壬申の年の功績をもってである。
初めて内舎人90人を任命して太政官において列見した。正五位上忌部宿祢色布知卒。詔贈從四位上。以壬申年功也。」始補内舍人九十人。於太政官列見。
「壬申の年」とは壬申の乱(672)のことをいっていますが、忌部色布知がどのような活躍をしたのかは明らかではありません。忌部氏は中臣氏と同じく祭祀に携わる氏族で、色布知は持統天皇4年(690)正月1日、天皇即位の際に三種の神器を奉ったと『日本書紀』に記録されています。
内舎人とは、律令で定められた、太政官の中務省に所属する職員で、以下のように規定されています。
職員令 第3条 中務省
内舎人 定員90人。職掌は、帯刀して宿衛すること、雑使(宮中の雑務)に供奉(奉仕)すること。駕行(行幸)の際には前後に分け警衛すること。

天皇の護衛官ですね♨️
「内」だけで宮中を意味します。

90人ということは、定員いっぱいまで任命したということですね。
勅(大宝令遵守、大税の貯蓄)、七道使発遣
6月8日(己酉) 次のように勅があった。「すべての庶務は新令に基づくこととし、また国宰(国司)・郡司は大税の稲を貯蓄すること。必ずすべて法の規定に従うこと。もし怠りがあればその罪に従って罰することとする」と。
この日、使いを七道に派遣し、新令に基づいて行政を行い、大税を給付する場合について説明させた。ならびに、新しい国印の見本を配布した。勅。凡其庶務。一依新令。又國宰郡司。貯置大税。必須如法。如有闕怠。隨事科斷。是日。遣使七道。宣告依新令爲政。及給大租之状。并頒付新印樣。

大宝令の規定が順次施行されるにあたり、七道(畿内以外の全国)にその決まりを周知するため七道使が発遣されました。
大税とは、稲を納める租税のことで、正税(しょうぜい)ともいいます。「大税を給付する」というのは、飢饉など非常の場合のことを言っています。

「おおちから」という読みからして国の一番重要な税ということが伝わりますね♨️
造薬師寺司任命など
6月11日(壬子) 正五位上波多朝臣牟胡閇と従五位上許曹倍朝臣陽麻呂を造薬師寺司に任命した。
以正五位上波多朝臣牟胡閇。從五位上許曾倍朝臣陽麻呂。任造藥師寺司。6月16日(丁巳) 王親(皇族)と侍臣を招き西の高殿で宴をし、各々差をつけて御器(食器)と帛(白い絹)を下賜した。
引王親及侍臣。宴於西高殿。賜御器膳并帛各有差。6月25日(丙寅) 季節の雨が降らないため、四畿内国に命じて祈雨をさせた。これらの国には今年の調を免除した。
以時雨不降。令四畿内祈雨焉。免當年調。
造薬師寺司、つまり薬師寺を造営を担当した役所です。もっとも、薬師寺はこのときにはほぼ完成しているため、寺の維持管理などを担当したものと思われます。(文武天皇2年(698)10月4日条)
調(ちょう、みつき)は、繊維製品を基本にしつつ、さまざまな地域特産物を民衆に納入させた役務です。今回祈雨に従事した四畿内国(大和国、河内国、山背国、摂津国)には、見返りに調を免除したということです。

ちなみに調はもともと、京(ここでは藤原京)と畿内国はそれ以外の国よりも負担が半減されています。

地域格差がすごいですね、、、
参考書籍など
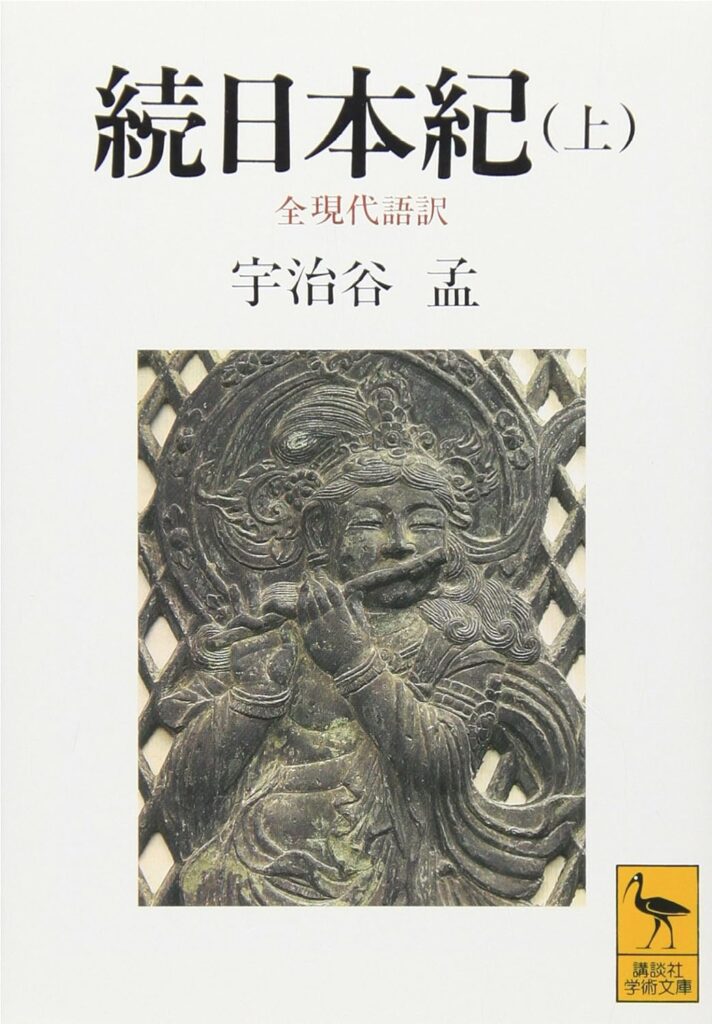
次回予告
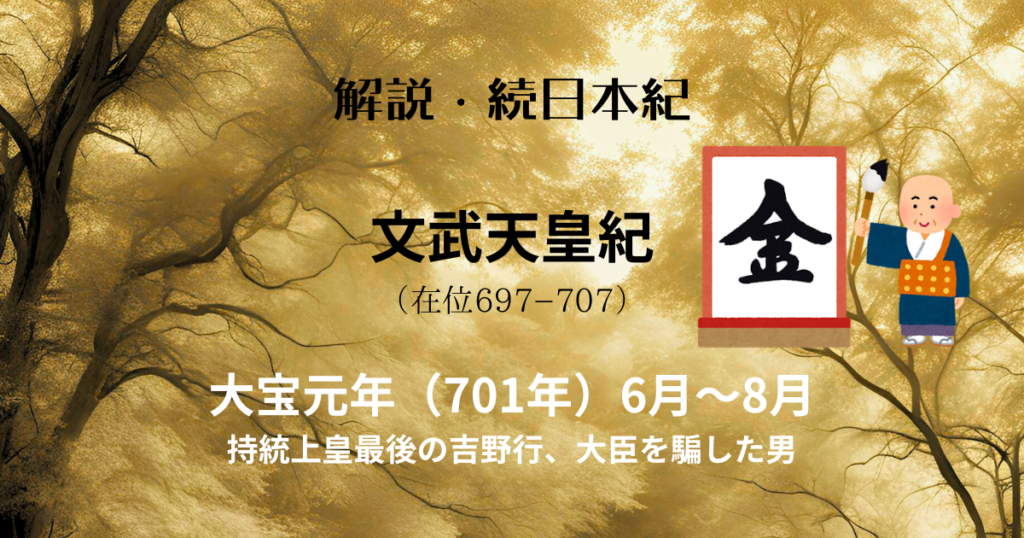

今回は律令が施行され、さまざまな対応がとられていたことがうかがわれる記事が多かったですね。

制度が変わって、朝廷で働いてる人も、地方で働いている人も対応に追われて大変だったでしょうね…!

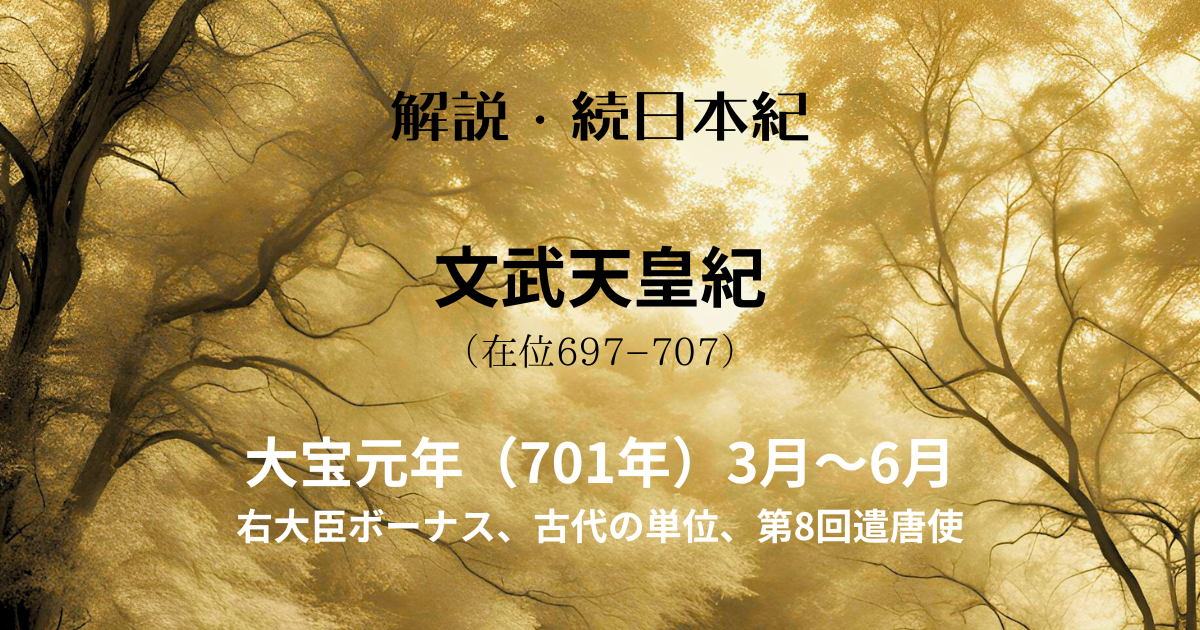


コメント